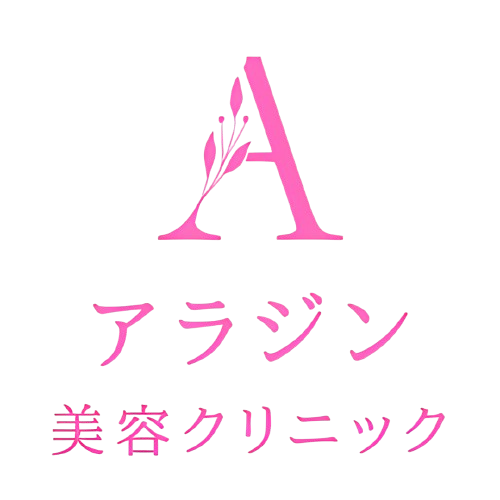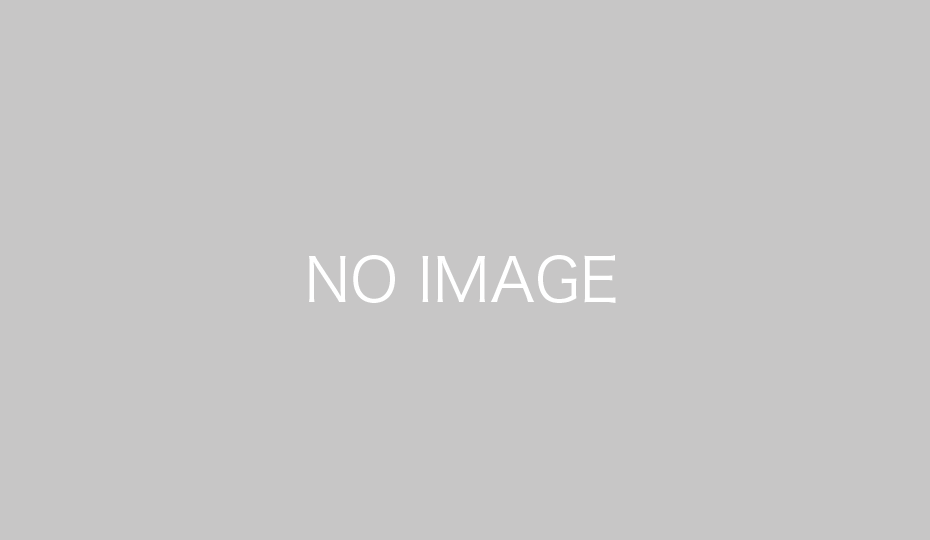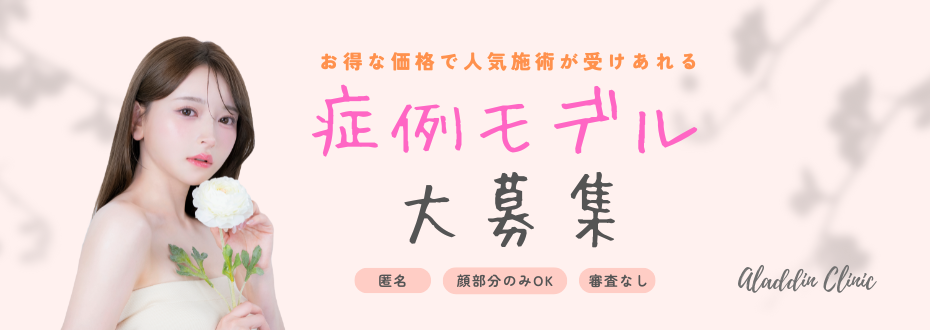美しくなるための糸リフト施術後、予期せず皮膚から糸が飛び出してきているのを発見した時の衝撃と不安は、計り知れないものがあるでしょう。「なぜ?」「どうすればいいの?」と気が動転し、一刻も早くこの状況を何とかしたいという焦りから、自分で糸を抜いたり、切ったりしてしまいたくなるかもしれません。
しかし、その行動こそが、取り返しのつかない事態を招く最も危険な選択です。自己判断による処置は、皮膚の下に細菌を侵入させ、深刻な感染症を引き起こすだけでなく、将来的な皮膚のひきつれや凹みの原因ともなり得ます。
ここでは、糸リフト後に糸が出てきてしまった際に絶対にやってはいけないNG行動から、その医学的な原因、放置するリスク、そしてクリニックで行われる正しい対処法まで、専門家の視点から一つひとつ丁寧に解説していきます。

国立琉球大学医学部医学科を卒業。国内大手美容クリニックなどで院長を歴任し、2024年アラジン美容クリニックに入職。
特にクマ取り治療では、年間症例数3,000件以上を誇るスペシャリストである。「嘘のない美容医療の実現へ」をモットーに、患者様の悩みに真剣に向き合う。
糸リフトで糸が出てきた?まず絶対にやってはいけない3つのNG行動
導入文で触れたように、糸リフト後に糸が皮膚から出てきた際、動揺から自己判断で対処しようとすることは、かえって事態を深刻化させる危険性をはらんでいます。美しくなるための施術が、思わぬ肌トラブルや将来的な変形の原因とならないよう、まずは冷静に状況を把握することが肝心です。
「早くなんとかしたい」という焦りの気持ちが、最も避けなければならない行動へと繋がってしまうのです。ここでは、パニック時に取ってしまいがちな具体的なNG行動を3つ挙げ、なぜそれが危険なのかを医学的な根拠に基づいて詳しく解説します。正しい知識を持つことが、ご自身の肌を守るための最初のステップとなります。
NG行動1|自分で糸を抜くまたはハサミで切る
飛び出してきた糸を異物と感じ、「一刻も早く取り除きたい」という衝動に駆られるのは自然な心理かもしれません。しかし、ご自身で糸を無理に引き抜いたり、眉毛用のハサミなどで切断したりする行為は、絶対に避けるべき最も危険な行動です。
その最大の理由は「感染」のリスクです。私たちの皮膚表面には、ブドウ球菌などの皮膚常在菌が多数存在しています。これらは通常、皮膚のバリア機能によって無害ですが、糸を伝って皮下組織に侵入すると、深刻な感染症の原因菌へと変貌します。
特に、無理に引き抜く際に生じる微細な傷は、細菌の絶好の侵入口となります。一度皮下で細菌が繁殖すると、抗生物質でも制御が難しい「バイオフィルム」という膜を形成することもあり、治療が長期化する恐れがあります。
さらに、糸リフトに使用される糸の多くには、「コグ」と呼ばれる小さなトゲがついており、これが皮下組織にしっかりと引っかかることでリフトアップ効果を発揮しています。この糸を無理に引き抜こうとすると、コグが周囲の正常な組織を傷つけ、強い痛みや内出血、腫れを引き起こす可能性があります。
また、途中で糸が切れて体内に残ってしまった場合、それが原因で将来的に皮膚のひきつれや凹み、しこりを生じさせるリスクも否定できません。衛生管理のされていないハサミで皮膚表面を傷つけるリスクも計り知れません。
NG行動2|指や物で糸を皮膚に押し込む
「とりあえず見えなくすれば大丈夫だろう」と考え、指やピンセットのようなもので糸を皮膚の内側へ押し込もうとする行為も、極めて危険です。これは、問題を解決するどころか、より根深く、複雑なトラブルの引き金となり得ます。
この行為は、皮膚表面に付着した細菌を、糸と一緒に皮下組織の奥深くへと押し込んでいるのと同じです。感染のリスクを人為的に高め、炎症をより広範囲に拡大させることになりかねません。
表面的な感染であれば比較的容易な処置で済むケースでも、深部での感染となると、場合によっては皮膚を切開して膿を排出する必要が出てくるなど、治療が大掛かりになる可能性があります。
また、糸が本来あるべき層からずれて不適切な位置に押し込まれると、身体がそれを「異物」と認識し、防御反応として糸の周囲に硬い組織(カプセル)を形成することがあります。
これが「異物肉芽腫(いぶつにくげしゅ)」と呼ばれるもので、触れるとしこりとして感じられたり、見た目にも不自然な膨らみとして現れたりすることがあります。
一度形成された肉芽腫は自然に消えることは稀で、除去するためには外科的な手術が必要になるケースも少なくありません。クリニックでの処置を、自ら困難にしてしまう行為だと認識する必要があります。
NG行動3|「そのうち治るだろう」と安易に放置する
「ほんの少ししか出ていないから」「クリニックに行くのが面倒」といった理由で、糸が出てきた状態を放置することも避けるべきです。たとえ痛みや赤みがなくても、皮膚から糸が露出している状態は、身体にとって異常事態であることに変わりはありません。
糸が露出した部分は、皮膚のバリア機能が破綻した「開いた傷口」と同じです。この小さな穴を通じて、日常的に細菌が皮下へ侵入し続けることになり、慢性的な軽度の炎症を引き起こす原因となります。炎症が長期化すると、その刺激によってメラニン色素が過剰に生成され、傷跡がシミのように黒ずんで残ってしまう「炎症後色素沈着」を招くことがあります。
また、糸の先端が常に皮膚を内側から刺激し続けることで、その部分の皮膚が徐々に薄く弱くなってしまう(菲薄化)ことも考えられます。最悪の場合、皮膚に完全に穴が開いてしまう「穿孔(せんこう)」に至るケースもあります。
そうなると、傷跡がより目立ちやすくなるだけでなく、治療にも時間を要することになります。もちろん、糸が本来の位置からずれているため、期待されていたリフトアップ効果も正常に得られているとは言えません。わずかな異常が、時間経過とともに審美的な問題と医学的な問題の両方を深刻化させる可能性があるのです。
万が一すでに触れてしまった場合の応急処置
これを読む前に、すでに出てきた糸に触れてしまった、あるいは少し引っ張ってしまったという方もいるかもしれません。強い不安を感じていることと存じますが、まずは落ち着いてください。これ以上、患部を刺激しないことが重要です。その上で、あくまで専門医の診察を受けるまでの「応急処置」として、以下の対応を行ってください。
最初に、清潔な流水で患部を優しく洗い流します。石鹸などの使用は刺激になる可能性があるため、水だけで十分です。その後、市販されている刺激の少ない消毒液(マキロンなど)を清潔なガーゼや綿棒に少量含ませ、傷口の周囲をそっと拭うように消毒します。
決して強く擦ったり、傷口の中に液体を流し込んだりしないでください。最後に、外部からの雑菌の付着や衣類との摩擦を防ぐため、清潔なガー-ゼや絆創膏で患部を軽く保護します。
ただし、これはあくまで感染リスクを少しでも低減させるための一時的な処置であり、問題の根本的な解決にはなりません。「消毒したから大丈夫」と自己判断して放置することは絶対に避けてください。応急処置を済ませたら、可及的速やかに施術を受けたクリニックへ連絡し、医師の診察を受けるようにしましょう。
なぜ糸リフトの糸は出てきてしまった?考えられる原因
前章で解説したNG行動を避けられたとしても、「そもそも、なぜこのような事態が起きてしまったのか」という根本的な疑問が残ることでしょう。この原因を客観的に知ることは、不必要な自己嫌悪や過度な不安から解放され、冷静に次のステップへ進むために非常に重要です。
糸が皮膚から出てきてしまう原因は、決して一つだけとは限りません。施術者の技術的な側面から、使用された糸の特性、術後の過ごし方、そしてご自身の体質まで、複数の要因が複雑に絡み合って発生することが少なくないのです。ここでは、考えられる主な原因を多角的に分析・解説していきます。
考えられる原因1|施術者の技術的要因と解剖学的理解
糸リフトは、医師の技術と経験、そして顔面の解剖学に対する深い理解が結果を大きく左右する施術です。糸が出てくるというトラブルの背景に、技術的な要因が関わっている可能性は否定できません。
最も一般的なのは、糸を挿入する「層(深さ)」が適切でなかったケースです。皮膚は表面から表皮、真皮、皮下脂肪、そしてSMAS(スマス)筋膜といった層構造をしています。
糸リフトでは、このSMAS筋膜の近くや皮下脂肪層内に糸を挿入し、組織をしっかりと引き上げるのが理想です。しかし、この挿入層が浅すぎると、糸が皮膚表面に近くなるため、表情の動きなどのわずかな力で皮膚を突き破り、外に露出しやすくなります。
また、糸の端の処理や固定が不十分であった場合も、糸が皮下で移動しやすくなる原因となります。特に、こめかみ付近の硬い組織(側頭筋膜)に糸を固定するような術式の場合、この固定が甘いと時間の経過とともに糸がずれ、先端が予期せぬ場所から出てくる可能性があります。顔の筋肉の動きや皮膚の厚みを考慮した適切なデザインがなされているかどうかも、重要な要素の一つです。
考えられる原因2|使用された糸の種類と特性のミスマッチ
現在、糸リフトには多種多様な種類の糸が存在し、それぞれ硬さ、太さ、柔軟性、そして組織を引っかけるための「コグ」と呼ばれるトゲの形状が異なります。これらの糸の特性と、施術を受ける方の皮膚の状態との間にミスマッチが生じた場合も、糸の露出に繋がることがあります。
例えば、皮膚が非常に薄い方や、目元や口元のように皮膚がよく動く部位に対して、硬すぎて柔軟性に欠ける糸を使用した場合、糸が皮膚の動きに馴染むことができず、先端が皮膚を刺激し続けて最終的に突き破ってしまうことがあります。
逆に、強力なリフトアップを求めるあまり、コグが大きすぎる、あるいは強すぎる糸を選択すると、そのコグが浅い層の組織に過剰な負荷をかけ、皮膚表面に凹みや引きつれを生じさせたり、糸の露出を引き起こしたりするリスクが高まります。
医師はカウンセリングを通じて、個々の肌質、皮下脂肪の量、たるみの程度、そして求める効果を総合的に判断し、最適な種類の糸を選択する必要があります。この選択が適切でなかった場合、トラブルの一因となる可能性があるのです。
考えられる原因3|術後の過ごし方と無意識の癖
施術が完璧に行われたとしても、術後のダウンタイム中の過ごし方によっては、糸が本来の位置からずれてしまうことがあります。クリニックから受けた注意事項を遵守することが、安定した結果を得るためには不可欠です。
特に注意が必要なのは、施術直後の過度な表情の動きです。大きく口を開けて笑ったり、あくびをしたり、硬いものを食べたりといった行為は、挿入したばかりでまだ組織に馴染んでいない糸に強いテンションをかけ、移動させる原因となり得ます。
また、無意識の癖も影響します。例えば、うつ伏せで寝る習慣があると、長時間にわたって顔の片側に圧力がかかり、糸がずれたり、皮膚から飛び出したりするリスクが高まります。
その他、施術部位を強く擦る、過度なマッサージを行う、歯科治療で口を大きく開け続けるといった物理的な刺激も同様です。飲酒や激しい運動、長時間の入浴など、血行を過剰に促進する行為も、腫れや内出血を増長させ、間接的に糸の位置に影響を及ぼす可能性があるため、術後しばらくは控えることが推奨されます。
考えられる原因4|ご自身の皮膚や骨格といった身体的要因
最後に、施術者や術後の過ごし方だけでなく、ご自身の体質が原因で糸が露出しやすくなるケースも存在します。これは「誰のせい」というわけではなく、個々人が持つ身体的な特徴に起因するものです。
代表的なのは、もともと皮膚が薄い、あるいは加齢によって皮膚が菲薄化している場合です。皮膚が薄いと、糸を覆う組織の厚みも当然少なくなるため、糸の輪郭が浮き出て見えやすくなったり、少しの刺激で糸が表面に出てきやすくなったりします。同様に、皮下脂肪が極端に少ない方も、糸を挿入する適切なスペースが限られるため、結果として浅い層に入りやすくなる傾向があります。
また、人それぞれ骨格や筋肉の付き方、表情の癖は異なります。特定の表情筋の動きが強い場合、その部位に挿入された糸に集中的に負荷がかかり、他の人よりも糸が移動・露出しやすいということも考えられます。
これらの身体的要因は、ご自身でコントロールできるものではありません。だからこそ、事前のカウンセリングで医師に自身の肌質や体質を正確に伝え、リスクについて十分に理解し、納得した上で施術を受けることが何よりも重要になります。
糸リフト後に出てきた糸の放置は危険!そのリスクと注意すべき症状
糸が出てきた原因について理解したところで、特に痛みや赤みといった自覚症状がない場合、「もう少し様子を見よう」と考えてしまう方がいるかもしれません。しかし、その安易な判断こそが、将来的に深刻なトラブルを引き起こす最も危険な選択肢となります。
皮膚から糸が露出しているという状態は、それ自体がすでに「正常ではない」サインであり、身体が何らかのSOSを発している証拠です。放置することで、当初は軽微であった問題が、感染症の重篤化や永続的な皮膚の変形など、治療が困難な状態へと発展するリスクを飛躍的に高めてしまいます。
ここでは、糸の放置がもたらす具体的な医学的リスクと、特に注意すべき危険な症状について詳しく解説します。
リスク1|感染症の慢性化と重篤化
糸が皮膚から露出している部分は、単なる「肌荒れ」ではなく、バリア機能が破綻した「開いた傷口」です。この小さな隙間から、皮膚表面に存在する常在菌が常に皮下組織へと侵入できる状態が続くことになります。
初期段階では身体の免疫機能によって大きな問題にならないかもしれませんが、放置することで軽度の感染と治癒を繰り返し、常に微弱な炎症が続く「慢性感染」の状態に陥るリスクがあります。
そして、体調不良やストレスなどで免疫力が低下したタイミングをきっかけに、細菌が急激に増殖し、「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」のような重篤な感染症へと発展する恐れも否定できません。蜂窩織炎を発症すると、広範囲にわたる強い赤み、腫れ、熱感、激しい痛みを伴い、場合によっては発熱などの全身症状が現れることもあります。
一度、感染が慢性化・重篤化してしまうと、内服の抗生物質だけではコントロールが難しくなり、長期間の点滴治療や、皮膚を切開して膿を排出する処置(切開排膿)が必要になるなど、身体的にも経済的にも大きな負担を強いる結果となります。
リスク2|皮膚のひきつれ・凹みといった整容的な問題
放置によるリスクは、感染症だけにとどまりません。整容面、つまり見た目の美しさにおいても、永続的な問題を残す可能性があります。糸の周囲で慢性的な炎症が続くと、身体は傷を修復しようとして、コラーゲン線維を過剰に産生します。その結果、糸と周囲の皮膚組織が異常に固く結びついてしまう「癒着(ゆちゃく)」を引き起こすことがあります。
この癒着が一度生じると、表情を動かした際に、その部分だけが不自然に引きつれたり、えくぼのような凹みやくぼみが生じたりする原因となります。笑顔や会話といった日常的な動作の中で、常に意図しない皮膚の変形が見られるようになるのです。
さらに深刻なのは、この癒着によるひきつれや凹みは、たとえ後から原因となっている糸をクリニックで除去したとしても、完全には元に戻らないケースがあるということです。癒着してしまった組織を剥がすのは非常に困難であり、整容的な問題が永続的に残ってしまうリスクをはらんでいます。早期に適切な処置を受けていれば防げたはずの問題が、放置によって取り返しのつかない傷跡になり得るのです。
リスク3|炎症後色素沈着としこり(異物肉芽腫)の形成
慢性的な炎症は、皮膚の色調や質感にも悪影響を及ぼします。炎症が続くことで、皮膚の色素細胞であるメラノサイトが刺激され、メラニンが過剰に生成されます。これにより、糸が出ていた部分やその周辺が、茶色いシミのように黒ずんでしまう「炎症後色素沈着」を招くことがあります。この色素沈着は、一度定着すると改善までに数ヶ月から数年単位の時間を要することもあります。
さらに、専門的なリスクとして「異物肉芽腫(いぶつにくげしゅ)」の形成が挙げられます。体内に留置された糸は、身体にとっては「異物」です。この異物の周囲で炎症が長期化すると、身体は異物を封じ込めて無害化しようとする防御反応として、その周りに肉芽組織という硬い組織の塊を形成します。
これが異物肉芽腫であり、触れると皮下にコリコリとした「しこり」として感じられます。このしこりは自然に消えることはほとんどなく、見た目にも不自然な膨らみとして現れる場合や、痛みや違和感の原因となることもあり、除去するためには外科的な切除術が必要になるケースも少なくありません。
【セルフチェック】放置は厳禁!クリニックへ相談すべき危険なサイン
糸が皮膚から出ていること自体が、速やかにクリニックを受診すべきサインです。その上で、もし以下に示すような症状が一つでも見られる場合は、すでに体内で重度の感染症が進行している可能性が極めて高く、一刻の猶予もありません。直ちに専門医の診察を受けてください。
- 赤み(発赤):糸の周囲や、その周辺の皮膚が明らかに赤みを帯びている。
- 腫れ(腫脹):施術部位が片側だけ異常に腫れている、または顔全体が腫れぼったく感じる。
- 熱感:糸が出ている部分に軽く触れると、他の部位の皮膚よりも明らかに熱く感じる。
- 痛み(疼痛):何もしていない状態でもズキズキとした拍動性の痛みがある、または軽く触れただけで激しい痛みを感じる。
- 膿(排膿):糸が出ている部分から、白や黄色、緑がかったドロリとした液体(膿)が滲み出ている。
これらの兆候は、身体が発する危険信号です。決して軽視せず、自己判断で様子を見るという選択は絶対にしないでください。速やかな受診が、症状の悪化を防ぎ、より早期の回復に繋がります。
クリニックでの正しい対処法と治療の流れ
出てきた糸を放置するリスクを理解し、速やかに専門医へ相談する必要性を感じたとしても、「実際にクリニックに行ったら、何をされるのだろうか」「痛みはあるのか、費用はかかるのか」といった、先の見えないことへの不安が、連絡をためらわせる一因になるかもしれません。
しかし、ご安心ください。適切な手順を踏めば、多くの場合は身体への負担が少ない処置で解決することが可能です。ここでは、実際にクリニックへ連絡してから治療が完了するまでの具体的な流れを4つのステップに分け、それぞれの段階で何が行われるのかを詳しく解説します。
ステップ1|まずは施術を受けたクリニックへ速やかに連絡・相談
異常を発見したら、まず最初に行うべきことは、様子を見ることなく、施術を受けたクリニックへ電話で連絡することです。ご自身の判断で他院を受診するのではなく、まずは施術を担当したクリニックに相談するのが原則です。
なぜなら、そこには施術の記録(カルテ)があり、医師が「どの種類の糸を、どの部位に、どの深さに、何本挿入したか」を正確に把握しているため、最も的確な原因究明と処置が可能となるからです。
電話の際には、落ち着いて以下の情報を伝えるようにすると、その後の対応がスムーズになります。
- いつ頃から異常に気づいたか
- 顔のどの部分から糸が出ているか
- どのような状態か(チクチクする、赤みがある、など)
- 痛み、腫れ、熱感などの自覚症状の有無
これらの情報をもとに、クリニック側は緊急性を判断し、できるだけ早い日程で診察の予約を調整してくれるはずです。決して遠慮したり、後回しにしたりせず、速やかに行動することが重要です。
ステップ2|医師による診察と状態の的確な診断
予約した日時にクリニックへ行くと、まずは医師による詳細な診察が行われます。医師は、糸が露出している部位を中心に、以下の点などを注意深く確認します。
- 視診:糸の露出の程度、周囲の皮膚の赤みや腫れの有無、膿の排出がないかなどを目で見て確認します。
- 触診:清潔な手袋を装着した上で、患部にそっと触れ、熱感の有無や皮下のしこり(肉芽腫の可能性)、糸の固定具合などを確かめます。
- ヒアリング:施術後の経過や、ご自身で感じている違和感、NG行動を取ってしまわなかったかなど、より詳しい状況を直接伺います。
これらの診察とヒアリングから得られた情報を総合的に分析し、医師は「なぜ糸が出てきたのか」という原因を推測するとともに、「現在の皮膚の状態(感染症の有無やその程度)」を的確に診断します。
この診断結果に基づき、これから行うべき最も適切な処置の方針が決定されます。疑問や不安な点があれば、この段階で遠慮なく質問し、しっかりと説明を受けるようにしましょう。
ステップ3|状態に応じた適切な処置(トリミング・抜糸と薬剤処方)
診断に基づき、具体的な処置が行われます。処置の内容は、糸の状態や感染の有無によって大きく異なりますが、主に以下のいずれか、または両方が行われます。
軽度で感染の兆候がない場合
感染の兆候がなく、単純に糸の先端がわずかに露出しているだけの場合は、皮膚の表面から出ている余分な部分の糸を、滅菌された医療用のハサミや器具で切断する「トリミング」という処置が行われます。
処置は非常にシンプルで、数分で終了します。痛みはほとんど感じないか、チクッとする程度で、通常は麻酔も必要ありません。
感染の疑いや問題が大きい場合
すでに感染を起こしている、糸が大きく露出している、皮下で糸が著しく移動しているといった場合には、原因となっている糸を根本から取り除く「抜糸」が必要となります。
多くの場合、局所麻酔を使用して痛みをコントロールした上で行われます。糸の挿入口や露出部から慎重に糸を抜き取りますが、状況によっては数ミリ程度の小さな切開を加えて糸を摘出することもあります。
また、感染を起こしている、あるいはそのリスクが高いと医師が判断した場合には、処置と並行して「抗生物質」の内服薬や外用薬(軟膏)が処方されます。これは体内の細菌を殺菌し、炎症を鎮めるために極めて重要ですので、必ず医師の指示通りに服用・使用してください。
ステップ4|処置後のアフターケアと効果への影響
処置が終わった後も、適切なアフターケアが重要です。処置当日の洗顔や入浴に関する注意点や、処方された薬剤の使用方法について、医師や看護師から説明がありますので、その指示に必ず従ってください。
処置に伴うダウンタイムは、トリミングであればほとんどありません。抜糸の場合でも、軽い腫れや内出血が数日間見られる程度で、日常生活に大きな支障をきたすことは稀です。
そして、多くの方が懸念される「リフトアップ効果への影響」ですが、過度に心配する必要はありません。トリミングの場合、糸の本体は皮下に残存しているため、リフトアップ効果への影響はほとんどないか、あってもごく軽微です。
一方、抜糸で糸を1本取り除いたとしても、他の多数の糸が組織を支えているため、全体的なリフティング効果が完全に失われるわけではありません。ただし、左右のバランスにわずかな変化が生じる可能性はあります。
もし仕上がりに物足りなさや左右差を感じるようであれば、状態が落ち着いた後(通常は数ヶ月後)に、追加で糸を挿入するなどの再治療を検討することも可能です。まずは今回のトラブルを確実に治癒させることが最優先となります。
まとめ
ここでは、糸リフトの施術後に糸が皮膚から出てきた場合の、危険なNG行動、考えられる原因、放置した場合の深刻なリスク、そしてクリニックでの適切な治療の流れについて詳しく解説しました。鏡を見て糸の存在に気づいた時、最も重要なことは、パニックにならず、そして「決して自分で触らない、抜かない、押し込まない」ということです。
ほんのわずかな糸の露出であっても、そこから細菌が侵入すれば感染症に、放置すれば皮膚のひきつれや色素沈着、異物肉芽腫といった、より複雑なトラブルへと発展する可能性があります。このような予期せぬ事態は稀に起こり得ますが、決して一人で抱え込む必要はありません。
大切なのは、自己判断で時間を置くのではなく、可及的速やかに施術を受けたクリニックの専門医へ連絡し、適切な診察と処置を受けることです。それが、ご自身の身体を守り、美しさを取り戻すための最も確実で安全な第一歩となります。もし少しでも不安や異常を感じた際には、決してためらわずに専門家へご相談ください。
アラジン美容クリニック福岡院では、「ウソのない美容医療の実現」をモットーに、患者様お一人ひとりの美のお悩みに真摯に向き合い、最適な治療をご提案しております。無駄な施術を勧めることなく、症状の根本的な原因にアプローチし、患者様の理想を実現するお手伝いをいたします。
また、福岡院限定で提供している特別な施術コース「クマフル」は、目元のクマ治療に特化した定額プランをご用意しております。ハムラ法、脂肪注入、目の下の脂肪取りなど、複数の治療法を組み合わせ、患者様お一人ひとりに最適な治療を提供いたします。目元のクマにお悩みの方は、ぜひこの機会にご利用ください。
LINE公式アカウントにて、カウンセリングや予約を受付しております。どなたでもお使いになられるクーポンもご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。