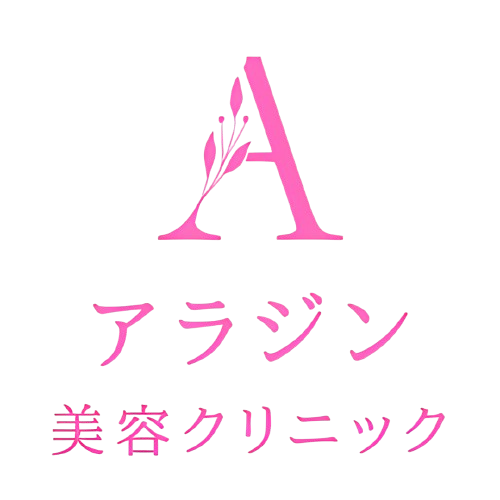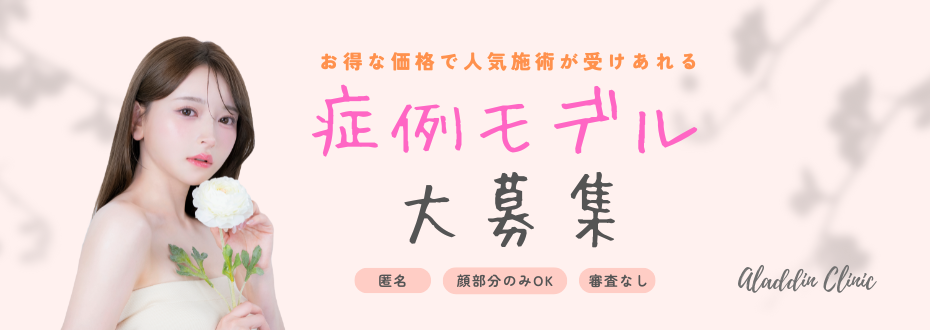ある日鏡を見て、「二重の幅が狭くなった?」「ラインが薄い…」と不安に感じていませんか?せっかく勇気を出して受けた二重埋没が取れてしまったかもしれないという考えは、誰にとってもショックなものです。「私の扱いが悪かったのかな…」とご自身を責めてしまうかもしれません。しかし、焦って自己判断したり、間違ったケアをしたりするのは禁物です。
ここでは、二重埋没が取れたかもしれないと感じているあなたの不安を解消するため、まずは本当に取れたのかを冷静に判断するセルフチェック方法から、取れてしまう医学的な原因、そして今すぐやるべきこと・やってはいけないことを専門家の視点で徹底解説します。さらに、次こそ後悔しないための進化した再手術の選択肢まで、あなたの未来を明るくするための知識を網羅的にお届けします。

国立琉球大学医学部医学科を卒業。国内大手美容クリニックなどで院長を歴任し、2024年アラジン美容クリニックに入職。
特にクマ取り治療では、年間症例数3,000件以上を誇るスペシャリストである。「嘘のない美容医療の実現へ」をモットーに、患者様の悩みに真剣に向き合う。
これって本当に二重埋没が取れたサイン?状態をセルフチェック
二重埋没法を受けた後、ふとした瞬間に鏡を見て「あれ?」と感じる変化は、大きな不安を伴うものです。期待していた二重のラインが薄くなったり、幅が狭くなったりすると、「もしかして埋没が取れたのでは?」と焦ってしまうのは当然のことでしょう。
しかし、結論を急ぐ前に、まずはご自身のまぶたの状態を客観的に観察することが重要です。まぶたは非常にデリケートで、体調や生活習慣によって日々微妙に変化します。
ここでは、本当に二重埋没の糸が緩んだり取れたりしている可能性を示す医学的なサインと、一時的な変化との見分け方を詳しく解説します。冷静に現状を把握することが、後悔のない次の一歩を踏み出すための最初のステップです。
二重埋没が取れた・取れかけの3大サイン?
二重埋没の糸が緩んだり、取れたりする際には、多くの場合、まぶたに特徴的な兆候が現れます。これらは単なる気のせいや一時的な変化とは異なる、構造的な変化の現れです。
もし以下の3つのサインのうち、いずれか、あるいは複数が継続的に見られる場合は、施術を受けたクリニックへ相談することを検討すべき段階かもしれません。一つずつ、なぜそのような変化が起こるのか、そのメカニズムと合わせて見ていきましょう。
①二重のラインが薄くなる・複数になる
埋没法は、まぶたの裏側から皮膚の下へ糸を通し、結ぶことで二重のラインを形成します。この糸の固定が緩むと、皮膚を内側へ引き込む力が弱まり、ラインの食い込みが浅くなります。
その結果、以前はくっきりとしていた二重のラインがぼやけたり、薄くなったりします。さらに緩みが進行すると、本来のラインとは別の場所に新たなシワが寄り、二重のラインが複数本現れる「三重(さんじゅう)」や、さらに複雑なラインの状態になることがあります。これは、糸が皮膚を支えきれなくなったサインの一つと考えられます。
②二重の幅が明らかに狭くなってきた
術後しばらくは、むくみ等の影響で二重の幅が広く見えることがありますが、それが落ち着いた後の安定期に入ってから、明らかに以前より幅が狭くなってきた場合も注意が必要です。特に、左右で幅に差が出てきた、日によって幅が大きく変わるなどの不安定さが見られるのは、糸の固定が弱まっている可能性があります。
時間の経過とともに皮膚が伸びて若干幅が狭くなることは自然な老化現象としても起こり得ますが、数週間から数ヶ月という短い期間で顕著な変化が見られる場合は、糸の緩みを疑うべき兆候と言えるでしょう。
③糸の結び目が埋まっていた部分のポコつきがなくなった
術後、まぶたを閉じた際に糸の結び目による微かな「ポコつき」を感じることがあります。これは通常、時間と共に組織に馴染んで目立たなくなりますが、ある日突然、これまで触れることができていた結び目の感触が完全になくなった場合、糸が切れたり、緩んで組織のより深層部へ移動してしまった可能性が考えられます。
もちろん、結び目を目立たなくする術式もありますし、元々ポコつきがほとんどないケースもあります。しかし、術後に確認できていた結び目が消失したのであれば、それは物理的な変化が起きた一つのサインと捉えることができます。
要注意!取れたと間違いやすい「偽のサイン」とは?
前述のサインが見られたとしても、即座に「二重埋没が取れた」と確定するわけではありません。特に術後数ヶ月以内など、状態が完全に安定していない時期には、取れたサインと酷似した「偽のサイン」が現れることがあります。過度な不安に陥らないためにも、これらがなぜ起こるのかを理解し、冷静に見極めることが大切です。
最も一般的な「偽のサイン」の原因は「むくみ(浮腫)」です。私たちのまぶたの皮膚は非常に薄く、体内の水分バランスの影響を顕著に受けます。
例えば、前日に塩分の多い食事を摂った、泣いた、睡眠不足が続いている、といった要因でまぶたがむくむと、組織内の水分量が増加します。これにより、一時的に二重のラインが浅くなったり、幅が狭く見えたりすることがあります。
これは糸の固定に問題が起きたわけではなく、まぶた全体のコンディションによる一時的な変化です。多くの場合、この種のむくみは数時間から1日程度で自然に解消されます。
見分けるための重要なポイントは、症状の「持続性」です。朝起きた時に最もラインが不安定で、午後になると改善される、あるいは日によって状態が良い時と悪い時がある、という場合は、むくみや体調による影響の可能性が高いでしょう。
一方で、数日間から1週間以上、常にラインが薄い、幅が狭いといった状態が改善されずに続く場合は、糸の緩みを疑う必要性が高まります。慌てて判断せず、まずは数日間、まぶたの状態を注意深く観察してみることをお勧めします。
医学的に見る「取れやすい人」の特徴チェックリスト
二重埋没が取れる原因は、術後の過ごし方や医師の技術だけではありません。実は、施術を受ける方ご自身のまぶたの解剖学的な特徴や、無意識の癖が、糸の持続性に大きく影響することが医学的にも指摘されています。
これは決して「誰が悪い」という話ではなく、あくまで物理的なリスク因子を指すものです。ご自身のまぶたが、もともと埋没法が取れやすい特徴を持っていた可能性を知ることは、ご自身を責める気持ちを和らげ、次の選択肢を冷静に考える上で役立ちます。
以下のチェックリストで、ご自身の状態を確認してみましょう。
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| まぶたが厚く、指でつまむとぷっくりしている | まぶたの厚みは、皮膚そのものの厚みに加え、その下にある眼窩脂肪(がんかしぼう)やROOF(ルーフ)と呼ばれる脂肪の量に影響されます。脂肪が多いと、糸が組織を支える際に常に強い抵抗がかかり、緩みやすくなる傾向があります。 |
| アイプチやアイテープを長年使用しても跡がつきにくかった | 皮膚が硬かったり、ハリが強すぎたりする場合、糸で癖付けをしてもラインが定着しにくいことがあります。糸が皮膚の弾力に負けてしまい、固定が浅くなる可能性があります。 |
| 目を開くときに、おでこの筋肉を使って眉毛を上げる癖がある | 無意識に眉毛を上げて目を開く癖は、軽度の眼瞼下垂(がんけんかすい)の兆候である場合があります。この癖があると、まぶたを持ち上げる際に糸に常に余計な張力がかかり、負担が蓄積して緩みの原因となります。 |
| アレルギーなどで、目をこする癖がある | まぶたをこする物理的な刺激は、埋没糸にとって最大の敵の一つです。糸と周辺組織の固定を直接的に弱めてしまうため、無意識の癖であっても持続性に大きな影響を与えます。 |
| コンタクトレンズ(特にハード)を日常的に使用している | コンタクトレンズの着脱の際に、まぶたを強く引っ張る行為が習慣化していると、糸に負担がかかりやすくなります。特にハードコンタクトレンズは着脱時のまぶたへの物理的影響が大きいとされています。 |
※このチェックリストは、あくまで医学的な傾向を示すものです。当てはまる項目があったとしても必ずしも二重埋没が取れるわけではなく、逆に当てはまらなくても取れる可能性はあります。一つの目安としてご参考ください。
二重埋没ってなぜ取れてしまうの?二重埋没が緩む医学的根拠
ご自身のまぶたの状態をセルフチェックし、「やはり二重埋没が取れたのかもしれない」という結論に至ったとき、次に浮かぶのは「なぜ?」という純粋な疑問、そして「自分のせいだろうか」という後悔や罪悪感ではないでしょうか。
しかし、埋没糸が緩んでしまうのは、決して単一の原因で起こるわけではありません。そこには、ご自身のまぶたの特性といった不可抗力的な側面から、施術そのものに含まれる技術的な側面まで、複数の要因が複雑に関与しています。
ここでは、二重埋没が取れる医学的な根拠を客観的に解き明かし、その現象が誰にでも起こりうることをデータと共に解説します。正しい知識は、不要な自責の念から心を解放し、未来へ向けた最善の選択をするための力となるはずです。
あなただけのせいではない!埋没が取れる2つの要因
二重埋没のラインが消失、あるいは薄くなるという現象は、大きく分けて「ご自身の身体的な要因」と「施術に伴う医療技術的な要因」の2つに大別されます。
多くの場合、これらの要因が複合的に絡み合って結果として現れます。つまり、ラインが薄れたのは、必ずしも術後の過ごし方やケアのみが原因ではないということを、まずご理解いただくことが重要です。それぞれの要因について、公平な視点から見ていきましょう。
①ご自身の要因(解剖学的構造・生活習慣)
前章のチェックリストでも触れた通り、まぶたの解剖学的な構造は、埋没法の持続性に大きく影響します。例えば、まぶたの皮膚やその下にある脂肪(眼窩脂肪・ROOF)が厚い場合、糸には常にまぶたを折りたたもうとする力と、元に戻ろうとする組織の抵抗力との間の緊張が生まれます。
この抵抗力が強ければ強いほど、糸にかかる負担は増大し、結果的に緩みや断裂のリスクが高まります。また、目を強くこする、うつ伏せで寝るなどの生活習慣は、糸が固定されている組織に直接的な物理的ダメージを与え、固定を弱める原因となり得ます。
これらは個人の努力で改善できる部分もありますが、まぶたの厚みや骨格といった生まれ持った特徴は、不可抗力的な側面が大きいと言えるでしょう。
②医療技術的な要因(術式・糸・固定)
一方で、施術を行う医師側の技術や判断も、持続性を左右する重要な要素です。例えば、術式には糸を点で固定する「点留め」と、線で固定する「線留め」があり、一般的に点の数が多いほど、また線で固定する方が、力が分散されて持続しやすいとされています。
使用する医療用の糸も、その太さや素材、伸縮性によって強度や持続性が異なります。さらに、糸をまぶたのどの組織に、どの深さで固定するかも極めて重要です。浅すぎれば固定が弱くなり、深すぎれば不自然な引きつれの原因となる可能性があります。
担当する医師が、個々のまぶたの状態を正確に診断し、最適な術式、糸、固定点を選択できたかどうかも、結果に大きく関わってくるのです。
5年で約20%が経験する「ラインの緩み」
二重埋没が取れたと聞くと、何か特別なこと、あるいは「失敗」のように感じられるかもしれません。しかし、医学的な見地から見れば、この現象は一定の確率で起こりうるものとして認識されています。
二重埋没法の持続性に関する医学報告は数多く存在しますが、その結果は術式や個人の状態によって大きく異なります。例えば、古い術式では5年で30%以上のライン消失率が報告される一方、現代の改良された術式では10%未満に抑えられているという報告もあります。
これらの様々なデータを総合的に鑑みると、一般的に、5年以内に10%〜30%程度の方が何らかのラインの緩みを経験する可能性があるとされています。これは、決して「失敗」ではなく、埋没法という施術が構造的に持っている特性の一つと理解することが重要です。
この数字は、術式や患者様のまぶたの状態によって変動しますが、決して無視できるほど低い確率ではありません。これは、埋没法がメスを使わず、糸で組織を留めているという構造的な特徴に起因します。皮膚を切開して強固な癒着を作る切開法とは異なり、埋没法は常に糸の張力とまぶたの組織の弾力とがせめぎ合っている状態です。
日々の瞬き(1日に約1万5千~2万回)による微細な刺激や、加齢による皮膚の変化などが長期的に蓄積し、糸が緩んだり、組織が糸の力から外れたりすることは、ある意味で自然な経過とも言えるのです。
この客観的なデータは、「自分だけが運悪く取れてしまった」という孤独感を和らげてくれるはずです。二重埋没が取れることは、決して稀なケースではなく、施術を受けた人の5人から10人に1人が数年のうちに経験する「起こりうる現象」であると捉えることで、より冷静に次のステップを考えることができるでしょう。
再手術で後悔しないために知るべき「埋没法の進化」
過去に埋没法が取れてしまったという経験は、決して無駄にはなりません。むしろ、その経験があるからこそ、次に行う施術をより慎重に、そして賢く選ぶことができます。
そして幸いなことに、美容医療の技術は日々進歩しており、二重埋没法も例外ではありません。かつて主流であった単純な「点留め」や「線留め」だけでなく、持続性や審美性をさらに追求した、新しいアプローチの術式が登場しています。
例えば、持続性を格段に高めることを目指した「自然癒着法」という考え方があります。これは、単に糸の力で縛るだけでなく、糸をかける際に微細な処理を加えて組織同士の自然な癒着を促すことで、糸が緩んだり切れたりしても二重のラインが維持されやすくなることを狙った術式です。まるで切開法のような持続性を、切らずに実現しようというアプローチです。
また、他人に気づかれにくい自然さを極限まで追求した「シークレット法(※)」のような術式も開発されています。これは、糸の結び目をまぶたの表面ではなく裏側(結膜側)に作ることで、目を閉じた際に懸念される結び目のポコつきを解消し、より自然な見た目を実現するものです。
(※シークレット法は、クリニックによって呼称が異なる場合があります)
これらの進化した術式は、かつての埋没法が抱えていた「いつか取れるかもしれない」「結び目が気になる」といった懸念に応えるための選択肢です。一度取れてしまったからといって埋没法自体を諦めるのではなく、より自分の希望に合った、進化した術式があることを知っておくこと。それが、次こそ後悔しないための重要な第一歩となるでしょう。
二重埋没が取れたと感じて今すぐやるべき事・やってはいけない事!
二重埋没が取れてしまう医学的な背景をご理解いただくと、過度な自責の念は和らぎ、少し冷静に現状を見つめられるようになったのではないでしょうか。原因が分かった今、次に知りたいのは「では、具体的にどう行動すれば良いのか」という実践的な指針のはずです。
不安な気持ちから、つい自己流の対処をしてしまったり、あるいはどうして良いか分からず問題を先送りにしたりしがちですが、その初動が今後のまぶたの状態を大きく左右することもあります。
ここでは、「今すぐやるべき最善の行動」と、状態を悪化させないために「絶対にやってはいけないこと」を明確に解説します。さらに、多くの方が感じるクリニックへの連絡の気まずさを解消する具体的な方法まで、次の一歩を迷わず踏み出すためのサポートをします。
最初のステップ|まずは専門のクリニックへ相談を!
二重のラインに異変を感じた際に取るべき最も重要かつ唯一の正しい行動は、速やかに専門のクリニックで医師の診察を受けることです。セルフチェックである程度の推測はできても、まぶたの内部で何が起きているのかを正確に判断することは、専門家でなければ不可能です。自己判断で「まだ大丈夫だろう」と放置してしまうことには、いくつかの看過できないリスクが伴います。
一つ目は、左右差や不自然なシワが定着してしまうリスクです。例えば片方のラインだけが取れた状態で過ごしていると、無意識に左右の目の使い方に差が生まれ、表情の癖となって非対称な印象が固定化されることがあります。また、取れかけの糸が中途半端に組織を引っぱることで、本来のラインとは別の場所に新たなシワが刻まれてしまうケースも少なくありません。
二つ目は、まぶたの皮膚そのものへの負担です。不安定なラインを放置すると、皮膚の同じ箇所が何度も折れ曲がることで負担が蓄積し、皮膚が伸びてたるみの原因となったり、将来的な再手術の際にデザインの選択肢を狭めてしまったりする可能性があります。
専門医は、視診や触診を通じて、糸が本当に緩んでいるのか、切れているのか、あるいはむくみや他の要因が関係しているのかを的確に診断します。その上で、現状のリスクや、考えられる今後の選択肢について医学的根拠に基づいた説明を提供してくれます。不確かな情報に一喜一憂する時間を過ごすよりも、まずは専門家の診断を仰ぐことが、問題を解決するための最も確実で安全な近道なのです。
絶対NG!取れたかも?と思った時にやってはいけない3つの行動
不安な気持ちは、時に冷静な判断を鈍らせ、良かれと思って取った行動が、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。二重埋没が取れたかもしれないと感じた時、まぶたの状態をそれ以上悪くしないために、以下の3つの行動は絶対に避けるようにしてください。
①まぶたを強くこする・頻繁に触る
ラインの状態が気になり、指でなぞったり、引っ張ってみたりしたくなる気持ちは分かります。しかし、これは最も避けるべき行為です。まぶたへの物理的な刺激は、まだかろうじて留まっている糸の固定をさらに弱め、完全なライン消失を早めてしまう可能性があります。
また、デリケートなまぶたの皮膚を傷つけ、色素沈着や炎症を引き起こす原因にもなりかねません。不安な時こそ、意識的に「触らない」ことを徹底しましょう。
②アイプチやアイテープで無理にラインを補強する
取れてしまった二重ラインを、一時的にでも元に戻そうとアイプチ(二重のり)やアイテープを使用するのは非常に危険です。これらの製品に含まれる粘着成分は、皮膚への刺激が強く、かぶれ(接触性皮膚炎)やアレルギー反応を引き起こすリスクがあります。
さらに、テープを剥がす際の刺激や、のりによって皮膚が常に引っ張られる状態は、まぶたの皮膚を確実に伸ばし、たるみを助長します。一度伸びてしまった皮膚は元に戻すのが難しく、将来の再手術の選択肢にも影響を及ぼします。
③「そのうち治るかも」と自己判断で長期間放置する
埋没法の糸が自然に元の位置に戻ったり、再固定されたりすることは医学的にあり得ません。時間が経てば解決する問題ではなく、むしろ前述したように、左右差の定着や皮膚への負担といった新たな問題を引き起こす可能性の方が高いのが現実です。「クリニックに行くのが面倒」「気まずい」といった理由で放置することは、百害あって一利なしと心得ましょう。
「気まずい…」を解消するクリニックへの上手な伝え方・聞き方
いざクリニックへ連絡しようと思っても、「保証期間がとっくに過ぎているし…」「何年も前の施術だから、迷惑がられるのでは?」「クレームだと思われたらどうしよう」といった気持ちが、大きな心理的な壁となって立ちはだかることがあります。
しかし、心配は無用です。誠実なクリニックであれば、過去に施術した患者様のその後の経過を診ることは、医療機関として当然の責務であり、むしろ貴重な症例として真摯に対応してくれるはずです。
その上で、連絡する際の伝え方を少し工夫するだけで、心理的な負担はぐっと軽くなります。大切なのは、感情的にならず、「相談」というスタンスで、現在の状況を客観的に伝えることです。
以下に、電話やメールで使える具体的な文例をいくつかご紹介します。
【施術を受けたクリニックに連絡する場合】
「お世話になっております。〇年〇月頃に、貴院で二重埋没法を受けました〇〇と申します。最近、二重のラインが薄くなってきたように感じており、現在のまぶたの状態について一度診察していただくことは可能でしょうか。」
保証期間が切れている場合でも、この伝え方で全く問題ありません。ポイントは、
- まず、いつ頃施術を受けた誰であるかを名乗る。
- 「取れた!」と断定せず、「~ように感じる」と客観的な事実を伝える。
- 「診察・相談」をしたいという目的を明確にする。
【引越し等で、別のクリニックに相談する場合】
「初めてご連絡いたします。〇〇と申します。〇年前に他院で二重埋没法を受けたのですが、最近ラインが不安定になってきました。今後の治療についてご相談させて頂きたく、カウンセリングの予約をお願いできますでしょうか。」
このように伝えることで、スムーズに診察やカウンセリングの予約へと進むことができます。気まずい気持ちは誰にでもあるものですが、勇気を出して一歩を踏み出すことが、後悔しないための最善の策です。
二重埋没をもう失敗したくない!あなたに最適な賢い選択肢とは?
専門家への相談を決意し、具体的な行動へ踏み出す準備ができた今、次なるステップは「未来の選択」です。一度、二重埋没が取れたという経験をしたからこそ、「次こそは絶対に後悔したくない」という想いは、誰よりも強いはずです。その想いは、理想の目元を叶えるための何よりの原動力となります。
ここでは、再手術を検討する上で考えられる選択肢を一つひとつ丁寧に解説し、ご自身の価値観やライフプランに合った「賢い選択」ができるよう、知識の羅針盤となる情報をお届けします。
特に、近年大きく進化した「埋没法の中でのアップグレード」という、最も現実的で魅力的な選択肢に焦点を当てていきます。過去の経験を最高の未来に変えるための知識を、ここで手に入れてください。
最初の分岐点|再度「埋没法」か根本解決の「切開法」か
再手術を考えるとき、まず大きな分かれ道となるのが、再び糸で留める「埋没法」を選ぶか、皮膚を切開して二重を作る「切開法」を選ぶか、という選択です。それぞれに明確なメリット・デメリットがあり、どちらが優れているということではなく、ご自身のまぶたの状態や、何を最も重視するかによって最適な方法は異なります。
①再度「埋没法」を選ぶ場合
多くの方がまず検討するのが、再び埋没法で施術する方法でしょう。最大のメリットは、やはりその手軽さと可逆性にあります。メスを使わないため、一般的に切開法に比べてダウンタイムが短く、社会復帰もスムーズです。
また、万が一デザインが気に入らなかった場合に修正が比較的容易であるという安心感もあります。「切開にはやはり心理的な抵抗がある」「長期の休みは取れない」という場合には、有力な選択肢となります。ただし、一度取れた経験から「また取れてしまうのでは?」という不安が残るのも事実です。
②根本解決を目指す「切開法」を選ぶ場合
一方で切開法は、希望の二重ラインに沿って皮膚を切開し、内部の組織を処理して癒着させることで、半永久的な二重を形成する方法です。最大のメリットは、埋没法のように糸が緩んで元に戻ってしまう心配がほとんどない、その持続性の高さにあります。しかし、ダウンタイムが埋没法より長く、一度施術すると元に戻すことは困難です。
どちらの選択肢も魅力的ですが、一度取れた経験を持つ多くの方が抱くであろう「切開は怖い、でもまた取れるのも嫌だ」という気持ちに寄り添い、「進化した埋没法」という第三の道に焦点を当てて深掘りしていきます。
取れにくさ重視なら「自然癒着法」
「次こそ絶対に取れたくない、でも切りたくない」という願いに応えるのが、この「自然癒着法」というアプローチです。従来の埋没法が、糸の力(点や線)だけで皮膚を支えていたのに対し、自然癒着法は糸を固定する際に微細な穴を通して皮膚と深層の組織(瞼板や挙筋腱膜)との間に自然な癒着を促すのが最大の特徴です。
これにより、糸はあくまで癒着をサポートする役割となり、たとえ将来的に糸の力が弱まったとしても、形成された組織の癒着によって二重のラインが維持されやすくなります。
切開法に近い構造をメスを使わずに作り出すことを目指すため、10年以上効果が期待できる、持続性に特化した術式と言えます。まぶたが厚めの方や、過去に取れた経験から持続性を最優先したい場合に最適な選択肢です。
バレにくさ重視なら結び目が表に出ない方法(シークレット法)
「二重にはなりたいけれど、整形したことは絶対に気づかれたくない」という繊細なニーズに応えるのが、糸の結び目を工夫した術式です。一般的な埋没法では、糸の結び目が皮膚のすぐ下に埋め込まれるため、目を閉じた際に小さなポコつきとして現れることがありました。
これに対し、この方法では糸の結び目をまぶたの裏側(結膜側)に作ることで、皮膚の表面には一切の凹凸を残しません。目を閉じても、伏し目になっても、まるで生まれつきの二重のように極めて自然な仕上がりを追求できます。持続性も従来の埋没法と同等以上を確保しつつ、審美性、特に「バレにくさ」を極限まで高めた術式です。
まとめ
ここでは、二重埋没が取れてしまったという不安なサインを正しく見極める方法から、それが決してあなただけのせいではない医学的根拠、そして具体的な対処法までを詳しく解説しました。大切なのは、埋没糸が緩むのは決して珍しいことではなく、統計的にも起こりうる現象だと理解することです。
そして、最も重要なのは、一人で抱え込まず、まずは専門のクリニックで正確な診断を受けることです。現代の美容医療には、あなたの希望を叶えるための「自然癒着法」や「シークレット法」といった新しい選択肢も存在します。
ここで得た知識を武器に、ぜひ勇気を出してカウンセリングの一歩を踏み出してみてください。信頼できる医師と共に、あなたの理想やまぶたの状態に合った最適な方法を見つけることが、次こそ後悔しない、美しく自然な二重への最短ルートとなるでしょう。
アラジン美容クリニック福岡院では、「ウソのない美容医療の実現」をモットーに、患者様お一人ひとりの美のお悩みに真摯に向き合い、最適な治療をご提案しております。無駄な施術を勧めることなく、症状の根本的な原因にアプローチし、患者様の理想を実現するお手伝いをいたします。
また、福岡院限定で提供している特別な施術コース「クマフル」は、目元のクマ治療に特化した定額プランをご用意しております。ハムラ法、脂肪注入、目の下の脂肪取りなど、複数の治療法を組み合わせ、患者様お一人ひとりに最適な治療を提供いたします。目元のクマにお悩みの方は、ぜひこの機会にご利用ください。
LINE公式アカウントにて、カウンセリングや予約を受付しております。どなたでもお使いになられるクーポンもご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。