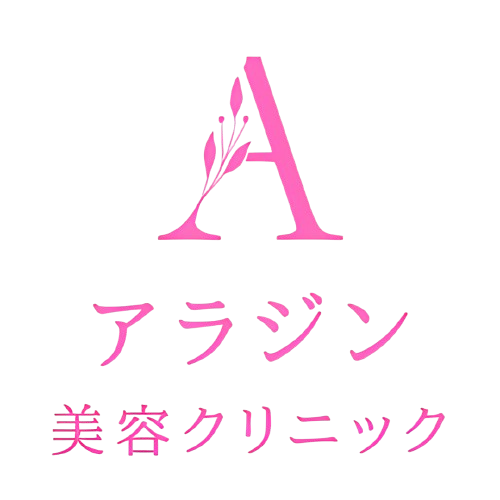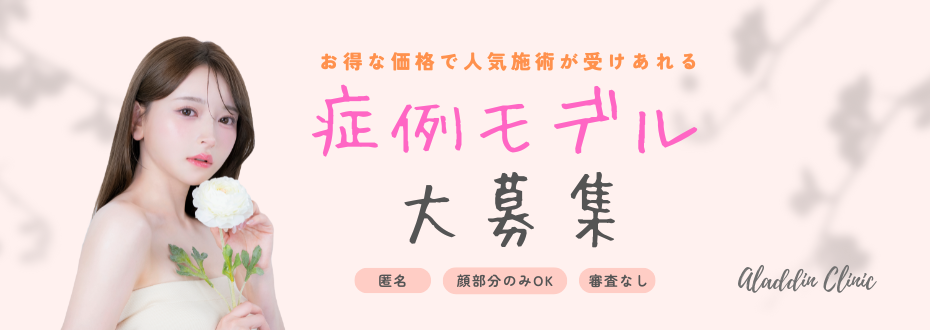最初、糸リフトを検討する段階では、「糸リフトに興味があるけれど、何歳から始めるのがベストなの?」「20代や30代前半ではまだ早い?」など、誰しもが多くの疑問や不安が募ります。
たるみケアとして人気の糸リフトですが、その最適な開始年齢については、多くの方が悩むポイントです。SNSでは「早く始めた方がいい」「ある程度の年齢になってから」と様々な情報が溢れ、どの情報を信じれば良いか迷ってしまうのも無理はありません。
しかし、美容医療の観点から言えば、何歳からという問いに対する答えは一つではありません。重要なのは年齢という数字ではなく、患者さんの「目的」です。
ここでは、将来のための「予防」なのか、現在の悩みの「改善」なのか、あなたの目的に応じた最適なタイミングを医学的根拠に基づいて徹底解説します。「まだ早いかも」という迷いで後悔しないために、疑問に明確にお答えします。

国立琉球大学医学部医学科を卒業。国内大手美容クリニックなどで院長を歴任し、2024年アラジン美容クリニックに入職。
特にクマ取り治療では、年間症例数3,000件以上を誇るスペシャリストである。「嘘のない美容医療の実現へ」をモットーに、患者様の悩みに真剣に向き合う。
糸リフトを始める最適なタイミングは「目的」によって異なります
「糸リフトは何歳から始めるべきか」という問いには、すべての人に共通する単一の「正解」が存在しません。
それは、美容医療が個々の現在の状態と、目指すべきゴールによって最適解を導き出すものだからです。特に糸リフトにおいては、その「目的」が、施術を受けるタイミングを決定する最も重要な鍵となります。
ご自身の現状が、将来的なたるみを「予防」したい段階なのか、それとも既に感じている変化を「改善」したい段階なのか。このご自身の目的意識によって、糸リフトに期待する効果やアプローチは医学的に異なります。
将来への「予防」が目的の場合!20代後半〜30代前半の選択
「20代で糸リフトはまだ早いのでは?」と感じるかもしれません。しかし、美容医療の領域において「予防」は非常に重要な概念です。20代後半から30代前半という時期は、多くの場合、目に見えるほどの大きなたるみはまだ顕在化していません。
しかし、肌の内部では、ハリや弾力を支えるコラーゲンやエラスチンといった成分の産生量が、20歳頃をピークに徐々に減少し始めています(この点は次の章で詳しく解説します)。
この時期に糸リフトを検討する方の多くは、「以前よりほうれい線の影が気になるようになった」「夕方になると顔が疲れて見える、むくみやすい」「フェイスラインが以前よりシャープでない気がする」といった、ごく初期の変化を感じ取っています。
この段階での糸リフトの最大の目的は、その初期変化をリセットすること、そして何より「将来のたるみを予防」することにあります。糸リフトで使用する医療用の糸は、皮下組織を物理的に引き締めるだけでなく、挿入された糸の周囲で「創傷治癒反応」と呼ばれるプロセスを引き起こします。この反応が、自身の線維芽細胞を活性化させ、新たなコラーゲン生成を促すのです。
本格的なたるみが生じる前に肌の土台を強化し、ハリを「貯蓄」しておく。これが、20代後半から30代前半に行う「予防的糸リフト」の大きな意義です。単に引き上げるだけでなく、肌質そのものを強化し、エイジングの進行速度を緩やかにするアプローチと言えます。
現在の悩みの「改善」が目的の場合!30代後半以降のアプローチ
30代後半から40代、50代にかけては、多くの方が具体的な「たるみ」の悩みに直面します。「鏡を見るたびに深くなるほうれい線が気になる」「口角が下がって不機嫌そうに見える」「フェイスラインが崩れ、頬の位置が下がってきた」といったお悩みです。
これらは、単なる皮膚表面の弾力低下だけではなく、皮膚を支える土台である皮下脂肪の減少や下垂、さらには骨格を支える「リガメント(支持靭帯)」のゆるみも関与して生じています。セルフケアや、ハイフ(HIFU)などの照射治療だけでは、満足のいく結果が得られにくくなってくる時期でもあります。
この段階での糸リフトの目的は、明確な「改善」です。つまり、すでに生じているたるみや組織の下垂を、物理的に引き上げて若々しい位置に戻すことが主眼となります。予防的なアプローチとは異なり、この場合は、より強力なリフティング力(牽引力)を持つコグ(トゲ)付きの糸や、持続性の高い糸を選択することが一般的です。
たるんでしまった組織をしっかりと持ち上げ、崩れたフェイスラインを再構築することで、視覚的な変化を実感しやすいのがこの時期の糸リフトの特徴です。もちろん、この年代であっても糸によるコラーゲン生成促進効果は期待できます。
リフトアップによる即時的な改善と、肌のハリや質感の向上という中長期的な効果を同時に目指せるため、総合的なエイジングケアとして非常に有効な選択肢となります。
なぜ美容では「予防」が重要?見えない老化の始まりについて
前の章では、糸リフトを検討するタイミングは「予防」と「改善」という2つの目的によって異なると解説しました。特に20代後半から30代前半の「予防」的アプローチについて、「まだ目に見えるたるみが無いうちから必要なのか」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、私たちが鏡を見て「たるみ」として認識する表面的な変化は、実は氷山の一角に過ぎません。その兆候が現れるずっと以前から、皮膚の深層部では静かな変化、すなわち「見えない老化」が確実に始まっています。多くの皮膚科学的研究において、肌のハリや弾力を支える真皮コラーゲンは、20歳頃をピークに年間約1%ずつ減少していくと報告されています。
この「見えない老化」のメカニズムを理解することこそが、「予防」という選択肢がなぜ合理的であり、将来の美しさにとって重要なのかを解き明かす鍵となります。
たるみの根本原因は皮膚の深層で起こる「リガメント(支持靭帯)」のゆるみ
一般的に「たるみ」というと、多くの方は皮膚表面のハリが失われること(弾力低下)を想像しがちです。もちろんそれも要因の一つですが、ほうれい線やフェイスラインの崩れといった、より構造的な「たるみ」の根本原因は、さらに深い層で起こっています。
顔の構造は、単純な一枚の皮膚ではなく、複数の層が重なってできています。表面から「皮膚(表皮・真皮)」、その下に「皮下脂肪」、さらに深層には「SMAS筋膜(スマスきんまく)」と呼ばれる表情筋を覆う線維性の膜があり、それらが複雑に組み合わさって骨格の上に乗っています。
ここで最も重要な役割を果たしているのが、「リガメント(Retaining Ligaments)」、日本語では「支持靭帯」と呼ばれる組織です。
リガメントは、顔の骨から皮膚やSMAS筋膜に向かって垂直に伸びる、強固な線維組織の束です。例えるなら、テントを支える「杭」や、建物の「柱」のような存在です。このリガメントが、皮膚や皮下脂肪、SMAS筋膜といった軟部組織を骨にしっかりと繋ぎ止め、重力に逆らって本来あるべき位置に保持しています。
しかし、このリガメントも加齢とともに弾力性を失い、徐々にゆるんでいきます。長年使用したゴムが伸びてしまう現象に似ています。この「柱」であるリガメントがゆるめば、当然、それが支えていた組織(脂肪やSMAS筋膜)は重力の影響を強く受け、下方へ、下方へと移動(下垂)を始めます。
この深層部での構造的な崩れが、結果として皮膚表面に「ほうれい線が深くなる」「頬の位置が下がる」「フェイスラインがもたつく」といった「たるみ」として現れるのです。
つまり、たるみは皮膚表面の問題であると同時に、顔の土台であるリガメントのゆるみという、解剖学的な構造の問題なのです。この事実こそが、20代後半といった早期から「予防」的なケアを検討する医学的な根拠となります。
【年代別】糸リフトの目的と期待できる効果とは?
第2章で解説したように、たるみの原因は皮膚の表面だけでなく、リガメント(支持靭帯)のゆるみといった深層部での構造的な変化にあります。この「見えない老化」の進行速度や、それが表面化するタイミングには個人差がありますが、年代ごとにある程度の傾向が存在します。
「糸リフトは何歳から」という問いに対する具体的な答えを求めている方にとって、ご自身の年代や、近い将来に直面する可能性のある悩みを具体的に知ることは、最適なタイミングを見極める上で非常に重要です。
ここでは、年代別に想定される主な悩みと、それに対する糸リフトの目的、そして期待できる効果について、網羅的に解説していきます。ご自身の現在の状況、そして未来の姿を想像しながら、糸リフトがどのような役割を果たすのかをご確認ください。
| 年代 | 主な悩み | 糸リフトの目的 | 期待できる効果 |
|---|---|---|---|
| 20代 | フェイスラインのもたつき、顔が大きく見える、将来のたるみが不安 | 予防・輪郭形成 | フェイスラインの引き締め、肌のハリ感UP、将来のたるみ予防 |
| 30代 | ほうれい線、口角の下がり、ハイフだけでは物足りない | 初期たるみの改善・予防 | ほうれい線・マリオネットラインの改善、肌質改善、コラーゲン生成促進 |
| 40代 | 全体的なフェイスラインの崩れ、頬のたるみ | 本格的なリフトアップ | シャープなフェイスラインの再形成、頬の位置を高く見せる、肌のハリ再構築 |
| 50代〜 | 深いシワ、首のたるみ | 全体的な若返り | 他の治療(ヒアルロン酸・ボトックス等)との併用で相乗効果 |
20代|「予防」と「輪郭形成」で将来に備える
20代は、医学的には本格的な「たるみ」が問題となる年代ではありません。しかし、この時期に糸リフトを希望される方の悩みとして多いのは、「生まれつきの骨格や脂肪のつき方でフェイスラインがぼんやりしている」「顔が大きく見えるのをすっきりさせたい」といった輪郭に関するものです。
また、美容への意識が高い方ほど、「将来のたるみを今から予防しておきたい」というニーズも強く見られます。
この年代での糸リフトは、たるみを引き上げるというよりも、皮下組織を引き締めてシャープなフェイスラインを形成する「輪郭形成」の側面が強くなります。
さらに、第2章で触れたコラーゲン減少が始まる時期でもあるため、糸を挿入することによるコラーゲン生成促進(肌のハリ感アップ)は、将来のたるみに対する「予防」として非常に有効なアプローチです。
30代|「初期たるみの改善」と「予防」の両立
30代は、多くの方が具体的なエイジングサインを感じ始める時期です。「20代の頃と比べて、ほうれい線の影が目立つようになった」「口角が下がってきた気がする」といった、リガメントのゆるみやコラーゲン減少に起因する「初期たるみ」が顕在化し始めます。また、ハイフ(HIFU)などの照射治療を経験し、「引き締め効果だけでは物足りなくなってきた」と感じる方も増える傾向にあります。
この年代の糸リフトは、「初期たるみの改善」と、これ以上の進行を防ぐ「予防」の両方を目的とします。ゆるみ始めた組織を物理的に引き上げ、ほうれい線やマリオネットライン(口角から下へのびる溝)を目立たなくさせると同時に、糸がコラーゲン生成を促すことで肌自体の土台を強化します。美容医療において、改善と予防のバランスが最も重要になるターニングポイントと言えるでしょう。
40代|「本格的なリフトアップ」でフェイスラインを再構築
40代になると、たるみは「初期」の段階を超え、より明確な「フェイスラインの崩れ」や「頬の下垂(ミッドチークのボリュームダウン)」として現れます。リガメントのゆるみも進行し、組織全体が下方に移動するため、顔全体の印象が大きく変わりやすい時期です。
この年代では、目的は明確に「本格的なリフトアップ」となります。予防的なアプローチというよりは、すでに生じているたるみを解剖学的に正しい位置(若い頃の位置)へとしっかりと引き上げることが最優先されます。
そのため、牽引力(引き上げる力)の強いコグ(トゲ)付きの糸を使用し、崩れたフェイスラインをシャープに再形成することが求められます。頬の位置が高くなることで、顔全体の重心が上がり、若々しい印象を取り戻すことが期待できます。
50代以降|「総合的な若返り」を目指すコンビネーション治療
50代以降は、たるみ(下垂)の問題がさらに進行するだけでなく、皮膚自体の菲薄化(薄くなること)や、長年の紫外線ダメージによる弾力低下、さらには皮下脂肪や骨の萎縮による「ボリュームロス(くぼみ)」など、複数のエイジングサインが複雑に絡み合って現れます。
このため、糸リフト単体でのアプローチには限界があるケースも増えてきます。糸リフトでたるんだ土台をしっかりと引き上げることは大前提ですが、それだけでは「若返り」としては不十分な場合があります。
例えば、糸リフトで引き上げた上で、くぼんでしまった頬やこめかみにヒアルロン酸を注入してボリュームを補ったり、表情によって刻まれる深いシワにボトックスを使用するなど、他の治療と組み合わせる「コンビネーション治療」が非常に効果的です。糸リフトを軸に、総合的な若返りを目指すアプローチが必要となります。
未来の美しさへの投資!糸リフトが「コラーゲン貯金」と言われる医学的根拠
第3章では、年代ごとの悩みと糸リフトの目的について解説しました。特に20代後半から30代といった早期の段階で糸リフトを選択することは、単なる「早期治療」という以上に、「予防」という重要な意味を持つことを確認しました。
この「予防」という概念は、美容医療の分野ではしばしば「未来の美しさへの投資」と表現されます。そして、糸リフトにおける予防的アプローチは、より具体的に「コラーゲン貯金」という言葉で例えられることがあります。
糸リフトの効果は、糸が挿入されている期間だけの物理的な引き上げ(リフティング)にとどまりません。糸が体内で吸収されるプロセスにおいて、肌の構造そのものに有益な変化をもたらす「中長期的な効果」こそが、糸リフトを「投資」たらしめる本質です。
ここでは、なぜ糸リフトが「コラーゲン貯金」と呼ばれるのか、その医学的な根拠について詳しく解説します。
糸が促す自己コラーゲン生成(Neocollagenesis)の仕組み
糸リフトで使用されるPDO(ポリジオキサノン)やPCL(ポリカプロラクトン)といった素材は、もともと外科手術の縫合糸として長年使用されてきた、生体適合性が高く安全な医療用素材です。これらの糸は、体内に挿入されると、数ヶ月から数年かけてゆっくりと加水分解され、最終的には体内に吸収されます。
このプロセスにおいて、体は挿入された糸を「異物」として認識します。そして、その異物を取り囲み、修復しようとする生体反応、すなわち「創傷治癒反応(Wound Healing Response)」が引き起こされます。これは、例えば皮膚が傷ついたときに、傷口が治癒していく過程と同様のメカニズムです。
この創傷治癒反応の過程において、糸の周囲(皮下組織)では、コラーゲンやエラスチンといった肌の弾性線維を産生する「線維芽細胞(せんいがさいぼう)」が強力に活性化されます。
活性化した線維芽細胞は、糸を足場にするようにして、その周囲に新しいコラーゲン線維を大量に産生し始めます。この現象を、医学用語で「Neocollagenesis(ネオコラゲネシス=コラーゲン新生)」と呼びます。
特に注目すべきは、このコラーゲン新生の過程で、若々しくしなやかな肌質に深く関わる「III型コラーゲン」の産生が促進されることが多くの研究で報告されている点です。III型コラーゲンは、通称「ベビーコラーゲン」とも呼ばれ、柔軟性の高い組織の構築に関与しますが、加齢とともに減少しやすいコラーゲンの一つです。
つまり、糸リフトは、糸が溶けて無くなった後も、糸の挿入ラインに沿って自己のコラーゲン組織が再構築され、それが肌の「ハリ」や「弾力」の土台として機能し続けるのです。これが、早期から糸リフトを行うことが「コラーゲン貯金」と呼ばれる医学的な根拠であり、将来的なたるみの進行を遅らせる「予防」効果の核心です。
(※医学的なメカニズムを分かりやすく説明するための比喩表現であり、効果には個人差があります。また、効果を保証するものではありません。)
【種類別】糸リフトに使われる糸の特徴と選び方
第4章では、糸リフトが「コラーゲン貯金」とも呼ばれる、自己のコラーゲン生成(Neocollagenesis)を促す医学的根拠について解説しました。このリフトアップ効果の持続期間や、コラーゲン生成の強さといった施術の「質」は、挿入する「糸の種類(材質)」によって大きく左右されます。
糸リフトと一言で言っても、使用される糸には様々な種類が存在します。どの糸が優れているかという絶対的な答えはなく、たるみの状態、皮膚の厚さ、求める効果(引き上げたいのか、ハリを出したいのか)によって最適な選択肢は異なります。
また、クリニックの施術方針、医師の技術や診断によって、採用している糸の種類や、それらをどのように(どの深さに、何本)使用するかは千差万別です。ここでは、現在主流となっている代表的な3つの糸の「材質」に着目し、その特徴と選び方の基準を専門的に解説します。
まずは、各材質の比較表をご覧ください。
| 材質 | 主な特徴 | 体内での吸収期間(目安) | 適したアプローチ |
|---|---|---|---|
| PDO (ポリジオキサノン) | しなやかで組織に馴染みやすい。牽引力とコラーゲン生成のバランスが良い。 | 約6ヶ月〜1年 | 初期たるみの改善、フェイスラインの引き締め、肌のハリ感アップ |
| PCL (ポリカプロラクトン) | 非常に柔軟性が高い。吸収が最も遅く、長期的なコラーゲン生成が期待できる。 | 約2年〜3年 | 持続性を重視する場合、予防(コラーゲン貯金)目的、ほうれい線など |
| PLLA (ポリ-L-乳酸) | 比較的硬めの材質。コラーゲン生成能力が強く、ハリを出す力に優れる。 | 約1年半〜2年 | しっかりとしたリフトアップ、頬のボリュームアップ、肌のハリ再構築 |
しなやかで馴染みやすい「PDO(ポリジオキサノン)」
PDO(ポリジオキサノン)は、数十年前から外科手術の縫合糸として世界中で使用されてきた実績があり、安全性と信頼性が非常に高い材質です。糸リフトの素材としても最も歴史が長く、広く普及しています。
最大の特徴は、適度な「しなやかさ」を持つ点です。皮下組織に挿入された後、表情筋の動きに合わせて柔軟にフィットするため、術後のひきつれ感(違和感)が比較的少ないとされています。
体内では約6ヶ月から1年かけてゆっくりと加水分解され吸収されますが、その過程で安定したコラーゲン生成を促します。リフティング力(牽引力)と肌質改善効果のバランスに優れており、20代〜30代の予防的アプローチから、40代以降の初期たるみの改善まで、幅広い年代とニーズに対応できるスタンダードな材質です。
持続期間が長くコラーゲン生成能力も高い「PCL(ポリカプロラクトン)」
PCL(ポリカプロラクトン)は、PDOやPLLAと比較して、最も体内で吸収されるまでの期間が長い(約2年〜3年)材質です。非常に柔軟性が高いという特性も併せ持っています。
吸収が遅いということは、それだけ長期間にわたって皮下組織を刺激し続け、コラーゲン生成(Neocollagenesis)を促すことができる、ということを意味します。そのため、第4章で解説した「コラーゲン貯金」としての役割を、より長期的に期待できる材質と言えます。
また、その柔軟性から、ほうれい線やマリオネットラインのような、よく動かす部位の引き上げにも適しています。1回の施術でできるだけ長い持続期間を希望する場合や、予防的なアプローチを重視する場合に有力な選択肢となります。
ハリを出す力に優れた「PLLA(ポリ-L-乳酸)」
PLLA(ポリ-L-乳酸)は、「スカルプトラ」といった注入剤(コラーゲンブースター)の主成分としても知られる材質です。
特徴は、PDOやPCLと比較して「硬さ」がある点です。この硬さが、たるんだ組織を内側からしっかりと支える「支柱」のような役割を果たします。また、コラーゲンを産生する線維芽細胞を刺激する力が強いとされており、リフティング効果に加えて、肌の「ハリ」や「ボリューム」を再構築する力に優れています。
吸収期間はPCLよりは短いものの、約1年半〜2年と比較的長めです。その硬さゆえに、挿入する層や部位には高度な技術が求められますが、頬のコケ(ボリュームロス)を伴うたるみや、しっかりとしたリフトアップ効果を求める場合に適した材質です。
糸リフトの限界と適用?カウンセリングで正直にお伝えすること
第5章では、PDOやPCLといった糸リフトに使用される糸の材質と、その特徴について解説しました。目的や肌の状態に応じて最適な糸を選択することは、満足のいく結果を得るための重要な要素です。
しかし同時に、糸リフトが「万能な治療ではない」という事実を理解することも、それ以上に重要です。どのような優れた治療法にも、医学的な適応と限界が存在します。
糸リフトへの期待値が過度に高すぎると、施術後に「思ったほどの効果が出なかった」というミスマッチが生じる可能性があります。信頼できる医療機関とは、施術のメリットだけでなく、これらの限界点についてもカウンセリングで正直に説明するものです。
ここでは、糸リフトだけでは改善が難しいとされるケースと、より良い結果を導き出すための他の選択肢について、誠実にお伝えします。
糸リフトだけでは改善が難しいケースとは?
糸リフトは、第2章で解説したリガメントのゆるみやSMAS筋膜の緩みを物理的に引き上げる、非常に有効なたるみ治療です。しかし、その効果には適応の範囲があります。
カウンセリングにおいて、もし以下のケースに該当すると医師が判断した場合、糸リフト単体での施術をお勧めしないか、または他の治療法を優先的に提案することがあります。
たるみ(皮膚の余剰)が重度である場合
糸リフトが最も効果を発揮するのは、一般的に軽度から中等度のたるみです。皮膚のゆるみが非常に強く、余剰皮膚(たるんだ皮膚)の量が多い場合、糸のコグ(トゲ)で組織を支えきれない、あるいは引き上げたとしても皮膚が寄ってしまい(ギャザー)、不自然な仕上がりになる可能性があります。
このような重度のたるみに対しては、外科的なアプローチである「フェイスリフト(切開リフト)」が、根本的な解決策として第一選択となる場合があります。
皮下脂肪の量が過度に多い場合
糸リフトは組織を引き上げる治療であり、脂肪を溶解・減少させる治療ではありません。フェイスラインや頬に皮下脂肪が厚くついている場合、その脂肪の「重み」によって、糸で引き上げる力(牽引力)が相殺されてしまいます。
結果として、リフトアップ効果が十分に得られない、または効果の持続期間が著しく短くなる可能性があります。この場合、まず脂肪溶解注射や脂肪吸引などでボリュームを減らし、土台を軽くしてから糸リフトで引き締める、という段階的な治療が推奨されます。
骨格構造に起因する輪郭の問題である場合
フェイスラインがぼやけて見える、またはほうれい線が目立つ原因が、皮膚のたるみではなく、骨格の形状にあるケースも少なくありません。例えば、生まれつき顎が小さい(後退している)場合、首との境界が不明瞭に見えがちです。
また、頬骨の位置が低いと、中顔面が平坦でのっぺりとした印象になり、たるんで見えやすいことがあります。これらは、糸リフトで皮膚を引っ張っても解決が難しい問題であり、ヒアルロン酸注入などで骨格のサポート(ボリュームの補填)を行う方が、輪郭形成として効果的な場合があります。
より良い結果のためのコンビネーション治療という選択肢
糸リフト単体では難しいケースがあることを知ると、不安に思われるかもしれません。しかし、それは「治療法がない」という意味では決してありません。むしろ、現代の美容医療は、一つの治療法に固執するのではなく、複数のアプローチを組み合わせる「コンビネーション治療」によって、より自然で、より高いレベルの結果を追求する時代に入っています。
糸リフトは、たるみを「引き上げる(リフトアップ)」ことに優れた治療です。しかし、エイジング(老化)の悩みは、たるみ(下垂)だけでなく、「肌のゆるみ(弾力低下)」「ボリュームの減少(コケ)」「肌質の悪化(シワ・キメ)」など、複数の要素が同時に進行しています。
例えば、第3章の50代以降の項目でも触れましたが、たるみを糸リフトで引き上げつつ、加齢によって減少した頬やこめかみのボリュームをヒアルロン酸注入で補う、あるいは、糸リフトで土台を持ち上げる前に、HIFU(ハイフ)を照射してSMAS筋膜と皮下組織を引き締めるなど、この引き締めと引き上げの併用は、リフトアップ効果を最大化し、持続性を高めるための非常に有効な戦略です。
さらに、口角を下げる筋肉の働きをボトックス注射で緩和し、糸リフトの上昇ベクトルをサポートする方法や、皮膚表面のハリや質感をダーマペンやポテンツァなどで改善し、深層と浅層の両方からアプローチする方法もあります。
重要なのは、ご自身の現在の状態を解剖学的に正しく診断し、糸リフト、HIFU、注入治療といった数多くの選択肢の中から、最適な「設計図」を描くことです。これが、医師によるカウンセリングの最も重要な役割です。
後悔しないために知るべき重要事項!リスク・流れ・安全対策
第6章では、糸リフトの限界と、より良い結果を導くためのコンビネーション治療について解説しました。施術への理解が深まったところで、次はいよいよ現実的なステップ、すなわち施術を受ける決断のフェーズです。
この段階で最も大きな不安要素となるのが、「どのようなリスクがあるのか?」そして「施術後、どのような経過をたどるのか?」という2点に尽きるでしょう。 美容医療は、魔法ではありません。他の医療行為と同様に、効果と表裏一体の副作用やリスクが必ず存在します。
ここでは、後悔しない選択のために、クリニックとして透明性を持って開示すべき客観的なリスク情報、当院の安全対策、そして具体的な施術の流れとダウンタイムの過ごし方について、詳しく解説します。
起こりうるリスク・副作用の客観的情報
糸リフトは、外科的な切開リフトと比較して身体的負担が少ない低侵襲治療とされていますが、針と糸を皮下組織に挿入する以上、以下のようなリスクや副作用が生じる可能性があります。これらは時間の経過とともに軽快するのが一般的ですが、その目安を知っておくことは非常に重要です。
腫れ・むくみ
麻酔液の注入や、組織が糸という異物に反応することで、術後に腫れやむくみが生じます。多くの場合、術後2〜3日目をピークとし、1〜2週間程度で徐々に落ち着いていきます。
内出血
施術中に針が皮下の毛細血管にあたると、内出血(青あざや黄み)が生じることがあります。コンシーラーで隠せる程度がほとんどですが、完全に消えるまでには1〜2週間ほど要する場合があります。
痛み・違和感
術後は、麻酔が切れると鈍い痛みや、糸が挿入されている部分に触れた際の痛みを感じることがあります。通常は処方される鎮痛剤でコントロール可能であり、数日〜1週間程度で軽減します。
ひきつれ感・ツッパリ感
糸で組織を引き上げているため、術後しばらくは、笑ったり口を大きく開けたりした際に、皮膚が引っ張られるような「ひきつれ感」や違和感が生じます。これは糸が組織に馴染んでいく過程で起こる正常な反応であり、多くは2週間〜1ヶ月程度で自然に解消されます。
感染
頻度は非常に稀ですが、糸の挿入部位から細菌が侵入すると、赤み、腫れ、熱感、痛みが続く「感染」を起こす可能性があります。予防的な抗生剤の内服を行いますが、万が一これらの症状が出た場合は、直ちにクリニックでの処置(抗生剤の点滴や糸の抜去など)が必要となります。
安全性を最大限に高めるための取り組み
上記のようなリスクをゼロにすることは不可能ですが、その発生率を最小限に抑え、万が一発生した際にも迅速かつ適切に対応することが、医療機関としての責務です。
糸リフトの安全性と結果は、医師の技術と知識に大きく依存します。顔には重要な神経や血管が複雑に走行しています。神経損傷などの重篤な合併症を回避するだけでなく、どの層にどの糸を挿入すれば最も安全かつ効果的かを正確に見極め、施術を行う必要があるでしょう。
また、感染リスクを予防するため、医療機器の滅菌・消毒はもちろんのこと、使用する糸や針はすべて滅菌パックされた使い捨て(ディスポーザブル)製品を使用は当たり前です。
さらに、施術後の不安な時期を安心して過ごすため、術後の定期検診(例:1週間後、1ヶ月後など)を設けるべきです。万が一、強い痛みや腫れなど予期せぬ症状が出た場合に備え、緊急時の連絡体制も整えることです。
カウンセリングから術後までの流れとダウンタイムの過ごし方
施術当日の具体的なイメージを持つことで、不安はさらに軽減されます。一般的な流れと、術後のダウンタイムの過ごし方について解説します。
カウンセリング・診察
まずは医師が肌の状態、たるみの程度、骨格を詳細に診察します。第1章で解説した「目的」をヒアリングし、最適な糸の種類や本数、挿入デザインを決定します。リスクやダウンタイムについても、この場で改めて詳しく説明します。
- 同意書作成・お会計
施術内容にご納得いただけましたら、同意書にサインをいただき、お会計へと進みます。 - 洗顔・写真撮影
施術前にメイクを落としていただきます。施術前後の比較のため、カルテ用の写真撮影を行います。 - 麻酔・デザイン
施術部位に局所麻酔(またはご希望により笑気麻酔など)を行います。麻酔が効くまで待つ間に、皮膚表面に糸の挿入ラインを正確にマーキング(デザイン)します。 - 施術
デザインに沿って、清潔操作のもと、糸を丁寧に挿入していきます。施術時間は、本数や範囲にもよりますが、おおむね30分〜1時間程度です。 - 冷却・術後説明
施術部位をアイシング(冷却)し、腫れを最小限に抑えます。鏡で仕上がりを確認いただいた後、術後の注意事項や内服薬(抗生剤、鎮痛剤など)について説明し、ご帰宅となります。
ダウンタイムの過ごし方
| 期間 | 主な症状 | 推奨される過ごし方 |
|---|---|---|
| 術直後〜3日目 | 腫れ・むくみ(ピーク)、麻酔による違和感、鈍痛、軽度の内出血。 | ・処方された抗生剤・鎮痛剤を指示通り服用。 ・長時間の入浴、サウナ、飲酒、激しい運動は避ける。 ・就寝時は枕を高くすると腫れが引きやすい。 ・洗顔やメイクは翌日から可能な場合が多いが、挿入部を強く擦らない。 |
| 4日目〜1週間 | 大きな腫れが引き始める。内出血が黄色く変化。ひきつれ感が出始める。 | ・引き続き、血行が良くなる活動(激しい運動、サウナ等)は控える。 ・口を大きく開ける動作(歯科治療、大きな食べ物)は避ける。・顔のマッサージは厳禁。 |
| 1週間〜2週間 | 腫れや内出血は、ほぼ目立たなくなる。ひきつれ感や違和感が残る時期。 | ・軽い運動は可能になる場合がある(医師の確認推奨)。 ・ひきつれ感は糸が馴染む過程の正常な反応のため、安静に過ごす。 |
| 1ヶ月後 | ひきつれ感や違和感がほぼ解消し、糸が組織に馴染む。リフトアップ効果が安定。 | ・ほぼ通常の生活が可能。 ・ハイフや顔のマッサージを受ける場合は、必ず医師に時期を相談する。(一般的に術後1〜2ヶ月は避ける) |
まとめ
糸リフトを何歳から始めるべきか、その答えは年齢ではなく「予防」と「改善」のどちらを目的とするかにあることを解説しました。肌の老化は、目に見えない皮膚の深層部、コラーゲンやリガメント(支持靭帯)のゆるみから静かに進行しています。
そのため、たるみが深刻化する前に始める20代後半や30代からの「予防」的アプローチは、将来の美しさへの「コラーゲン貯金」という非常に合理的な投資と言えます。もちろん、30代後半や40代以降で顕在化したたるみを「改善」するためにも糸リフトは強力な選択肢です。
大切なのは、「まだ早い」「もう遅い」と自己判断でタイミングを逃すことではなく、ご自身の現在の肌状態と目的に合った最適な治療法を見極めることです。肌状態や骨格を正確に診断し、糸の種類や本数、他の治療との組み合わせも含めて最適なプランをカウンセリングで確認してみましょう。
アラジン美容クリニック福岡院では、「ウソのない美容医療の実現」をモットーに、患者様お一人ひとりの美のお悩みに真摯に向き合い、最適な治療をご提案しております。無駄な施術を勧めることなく、症状の根本的な原因にアプローチし、患者様の理想を実現するお手伝いをいたします。
また、福岡院限定で提供している特別な施術コース「クマフル」は、目元のクマ治療に特化した定額プランをご用意しております。ハムラ法、脂肪注入、目の下の脂肪取りなど、複数の治療法を組み合わせ、患者様お一人ひとりに最適な治療を提供いたします。目元のクマにお悩みの方は、ぜひこの機会にご利用ください。
LINE公式アカウントにて、カウンセリングや予約を受付しております。どなたでもお使いになられるクーポンもご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。