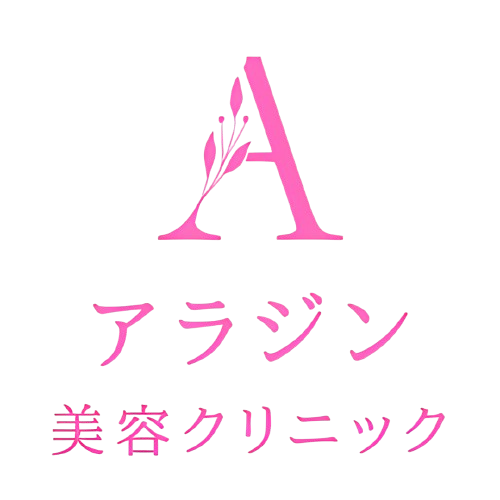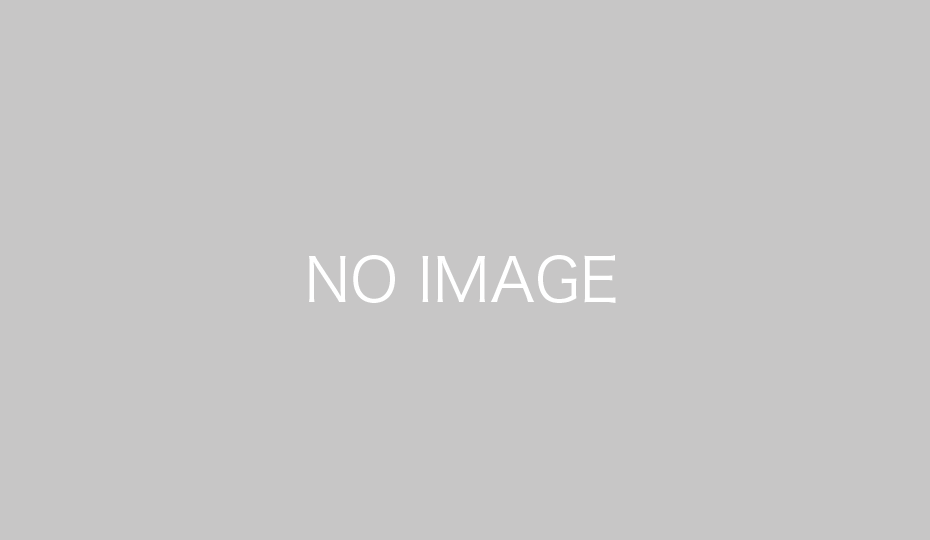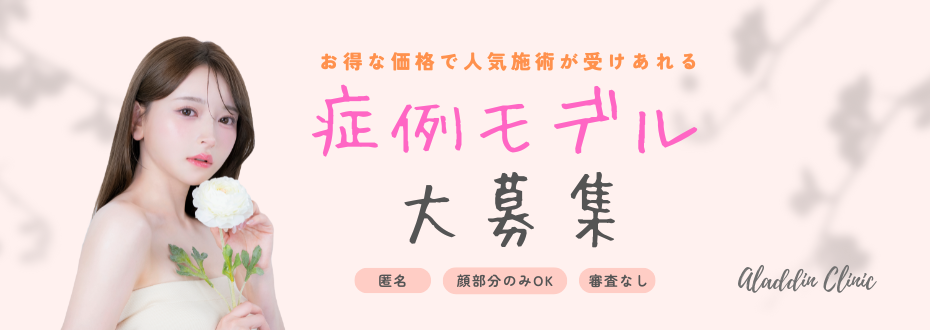「季節の変わり目になると、決まって体調を崩してしまう」など、そんな悩みを抱える一方で、周囲には一年を通してエネルギッシュに活動している免疫が強い人がいます。その違いは、一体どこにあるのでしょうか。
多くの人は「睡眠・運動・栄養」といった習慣の違いを想像するかもしれません。しかし、もしあなたが「健康のために人一倍努力しているのに、なぜか不調が続く」と感じているなら、その不調の意外な正体は、頑張りすぎということにあるかもしれません。
ここでは、一般的な健康論では見過ごされがちな、免疫システムを支える5つの生理学的原則を深掘りします。さらに、なぜ真面目な人ほど免疫のバランスを崩しやすいのか、そのメカニズムを精神神経免疫学の観点から専門的に解説します。

国立琉球大学医学部医学科を卒業。国内大手美容クリニックなどで院長を歴任し、2024年アラジン美容クリニックに入職。
特にクマ取り治療では、年間症例数3,000件以上を誇るスペシャリストである。「嘘のない美容医療の実現へ」をモットーに、患者様の悩みに真剣に向き合う。
免疫が強い人に共通する5つの生理学的原則?
免疫が強い人と聞くと、どのような姿を想像するでしょうか。多くの場合、「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」といった模範的な生活習慣が想起されます。
これらは間違いなく重要です。しかし、なぜそれらの習慣が重要なのか、その本質的な理由、すなわち身体のシステムを支える「原則」レベルで理解している人は多くありません。
ここでは、免疫システムが最適に機能するために欠かせない、5つの「生理学的原則」について深掘りします。習慣から一歩進んだ、人体の根本的な仕組みへの理解は、ご自身の不調を解き明かす鍵となるはずです。
原則1|最大の免疫器官「腸管」のバリア機能が最適化されている
免疫を語る上で、腸の存在を無視することはできません。全身の免疫細胞の約7割が集中していることから、腸管は「最大の免疫器官」と呼ばれています。その役割は、栄養素を吸収するという重要な機能と同時に、病原体や異物といった有害なものが体内に侵入するのを防ぐ「バリア」としての機能です。
このバリア機能の最前線が、腸の粘膜細胞同士を強固に結びつける「タイトジャンクション」と呼ばれる接着装置です。健康な状態では、このタイトジャンクションが固く閉じ、必要な栄養素だけを選択的に通過させ、細菌や未消化の食物、毒素などの侵入をブロックしています。
しかし、食生活の乱れやストレス、薬剤などの影響でこの結合が緩むと、本来ブロックされるべき異物が血中に漏れ出してしまいます。これが、いわゆる「リーキーガット(腸管壁浸漏症候群)」と呼ばれる状態です。
異物の侵入は、全身の免疫システムを過剰に作動させ、慢性的な炎症を引き起こす一因となります。腸管バリアの最適化は、免疫システムが不要な戦闘にリソースを割かず、本来の敵に集中するための大前提と言えるでしょう。
原則2|免疫細胞の働きを支える「深部体温」が適切に維持されている
免疫細胞もまた、体内の化学反応によって活動する細胞の一種です。そして、体内のほぼすべての化学反応(酵素反応)は、特定の温度域で最も効率よく進みます。免疫機能において、その指標となるのが「深部体温(中枢体温)」、すなわち脳や内臓といった身体の中心部の温度です。
一般的に、深部体温が36.5℃から37.0℃の範囲にあるとき、免疫細胞は最も活発に機能するとされています。例えば、体温が1℃低下すると、免疫機能は30%以上低下するという報告もあるほど、体温は免疫細胞の活動性、遊走能力、増殖能力に直結します。
現代社会では、運動不足による筋肉量の低下(筋肉は最大の熱産生器官です)、ストレスによる血流障害、空調の効いた環境での生活などにより、深部体温が理想とされる範囲を下回っているケースが少なくありません。自覚的な「冷え」がなくとも、体内が低温環境にあれば、免疫細胞はその能力を十分に発揮できず、いざという時の防御力が低下してしまうのです。
原則3|免疫の司令塔「自律神経」のバランスが乱れていない
免疫システムは、体内で独立して動いているわけではありません。その活動は、神経系や内分泌系(ホルモン)と密接に連携し、精緻なコントロールを受けています。この複雑なネットワークの「司令塔」として機能するのが、自律神経です。
自律神経は、活動時に優位になる「交感神経」と、休息・回復時に優位になる「副交感神経」の2つから成ります。免疫との関係で言えば、交感神経は主に顆粒球の働きを、副交感神経はリンパ球の働きをコントロールしているとされます。健康な状態とは、これら二つの神経がシーソーのようにバランスを取り、状況に応じて適切に切り替わっている状態です。
しかし、このバランスが崩れると、免疫システムにも混乱が生じます。例えば、後続の章で詳述しますが、精神的なストレスが持続すると交感神経が過剰に優位な状態が続きます。これにより、免疫機能が全体的に抑制されたり、逆に特定の部分で炎症がコントロールを失ったりします。
この神経・内分泌・免疫系の相互作用を研究する学問は「精神神経免疫学(Psychoneuroimmunology)」と呼ばれ、心と身体の繋がりを科学的に解明する分野として注目されています。
原則4|免疫細胞の材料と燃料となる「栄養素」が満たされている
免疫細胞が24時間365日、私たちの身体を守るために戦い続けるためには、膨大な「材料」と「燃料」が必要です。これらを供給するのが、日々の食事から得られる栄養素に他なりません。
まず「材料」として不可欠なのが、タンパク質です。抗体(免疫グロブリン)そのものがタンパク質から作られているほか、免疫細胞自体の主成分もタンパク質です。また、亜鉛やセレンといったミネラルは、免疫細胞が新しく分裂・増殖する際に必須の補酵素として働きます。粘膜バリアを強化するビタミンAも材料と言えるでしょう。
次に「燃料」として機能するのが、ビタミンB群です。これらは細胞内のエネルギー産生工場(ミトコンドリア)で、食物をエネルギー(ATP)に変換するサイクルを回すために不可欠です。ビタミンCやビタミンDも、免疫細胞の機能を調整し、その働きをサポートする重要な役割を担います。
重要なのは、これらの栄養素はどれか一つだけを大量に摂取すれば良いのではなく、オーケストラのように協調して働くという点です。また、女性の場合は特に、タンパク質や鉄(フェリチン)の不足が免疫機能の低下に直結しやすい傾向があります。
原則5|全身の細胞を活性化させる「血流」が良好である
原則4で述べた必須栄養素も、原則2で述べた体温も、それらを全身の細胞の隅々にまで届ける「輸送システム」がなければ機能しません。その役割を担うのが「血流」です。
免疫システムにおける血流の役割は、大きく二つあります。一つは「デリバリー」です。体内で異変(感染や損傷)が起こると、その情報が伝達され、免疫細胞が血液に乗って現場に急行します。同時に、免疫細胞が戦うためのエネルギー源となる酸素や栄養素も血液によって供給されます。
もう一つの役割は「回収」です。免疫細胞が戦った後の残骸や、細胞活動によって生じた老廃物を速やかに回収し、肝臓や腎臓へ運んで処理するのも血液の仕事です。
血流が滞ると、免疫細胞の現場への到着が遅れ、栄養や酸素も不足しがちになります。さらに老廃物が蓄積し、炎症が長引きやすくなります。特に、全身の血管の99%を占めるとされる毛細血管の血流が良好であることは、全身の細胞が活性化し、免疫が正常に機能するための最後の鍵を握っているのです。
その不調って頑張りすぎが原因かもしれません
第1章では、腸管バリアや深部体温といった、免疫を支える5つの生理学的原則について解説しました。これらは、健康を維持するための物理的な基盤です。しかし、食事に気を配り、運動も欠かさず、睡眠時間も確保しようと努力しているにもかかわらず、なぜか季節の変わり目に体調を崩したり、慢性的な疲労感が抜けなかったりするケースは少なくありません。
その原因は、身体的なケアの不足ではなく、むしろその努力の仕方や完璧を求める姿勢そのものにあるかもしれません。
ここでは、心理的なストレス、特に「頑張りすぎ」が、いかにして免疫システムを直接的に攪乱(かくらん)するか、そのメカニズムについて触れてみます。
ストレスホルモン「コルチゾール」の乱れが招く免疫抑制
ストレス社会において「コルチゾール」というホルモンの名前を耳にする機会は多いでしょう。これは主に副腎皮質から分泌されるホルモンで、身体がストレス(精神的・肉体的な負荷)に立ち向かうために不可欠な役割を果たします。
例えば、早朝に分泌量が増えて覚醒を促したり、血糖値を上昇させてエネルギーを供給したり、あるいは炎症を強力に抑えたりする作用があります。
短期的なストレス下において、コルチゾールは免疫系が暴走しないよう、その活動に適切なブレーキをかける役割(抗炎症・免疫抑制)を担います。問題は、このストレスが「慢性的」になった場合です。
仕事や人間関係での持続的な緊張、あるいは「完璧にこなさなければならない」という内面的なプレッシャーは、脳を介して副腎を刺激し続け、コルチゾールを慢性的に高レベルで分泌させます。高濃度のコルチゾールに長期間さらされると、免疫細胞(特にリンパ球など)の機能が全般的に抑制されてしまいます。これが、過度な緊張状態が続くと感染症にかかりやすくなるとされる一因です。
さらに、この状態が極度に進行すると、副腎が疲弊してコルチゾールの分泌リズム自体が乱れたり、逆に分泌量が低下したりすることもあります。そうなると、今度は免疫系に対するブレーキが効かなくなり、次の項目で述べるような炎症がコントロールできなくなるという、逆の事態も引き起こされ得ます。
自覚なき慢性炎症?心理的ストレスが引き起こすくすぶるような体内の火事
「炎症」と聞くと、怪我をした時の赤み・腫れ・痛みといった、目に見える「急性炎症」を想像するかもしれません。しかし、免疫の文脈で近年注目されているのは、自覚症状がほとんどないまま低レベルで持続する「慢性炎症」です。これは、体内で常に「くすぶるような火事」が起きている状態に例えられます。
従来、炎症は感染や外傷といった物理的な刺激によってのみ引き起こされると考えられていました。しかし、精神神経免疫学の研究は、純粋な心理的ストレスだけでも、この慢性炎症を惹起(じゃっき)し得ることを明らかにしています。
そのメカニズムは複雑ですが、一つには、ストレスが交感神経系を過剰に興奮させ、その結果、マクロファージなどの免疫細胞が活性化し、炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)を放出することが挙げられます。
前項のコルチゾールは、本来こうした炎症性サイトカインの産生を抑える働きがあります。しかし、慢性的なストレス下では、免疫細胞がコルチゾールの抑制命令に対して抵抗性を持つようになり、ブレーキが効かなくなるという現象も報告されています。
この自覚なき慢性炎症は、特定の臓器を攻撃するわけではなく、全身に影響を及ぼします。原因不明の倦怠感、集中力の低下、気分の落ち込み、あるいは肌荒れといった美容面での不調の背景にも、こうした心理的ストレスに起因する微細な炎症が関わっている可能性が指摘されています。
思考の癖と免疫システムの対話|身体の反応を決めるもの
コルチゾールの乱れや慢性炎症を引き起こす心理的ストレスとは、具体的に何を指すのでしょうか。重要なのは、ストレスとは出来事そのものではなく、「その出来事をどう捉えるか」という認知のプロセスに大きく依存する、という点です。
例えば、同じ「高い目標」が目の前にあっても、それを乗り越えるべき挑戦(チャレンジ)と前向きに捉える場合と、失敗が許されない脅威(スレット)と深刻に捉える場合とでは、身体の反応(ホルモンや自律神経の応答)は全く異なります。
特に、完璧主義的な傾向や、「~すべき」「~ねばならない」という「べき思考」が強い場合、脳は常に「脅威」にさらされていると認識し、交感神経を緊張させ続けます。日常生活の些細な出来事に対しても、身体が戦闘モード(闘争・逃走反応)を解除できなくなってしまうのです。
これは、免疫システムが、外界の病原体だけでなく、その人の「内なる対話」や「思考のパターン」にも絶えず耳を傾け、反応していることを意味します。健康のためにと完璧を目指すその努力が、皮肉にも身体を慢性的な緊張状態に陥らせ、免疫のバランスを静かに崩していく。これこそが、「頑張りすぎのパラドックス」の正体でしょう。
原因不明ではない!身体から送られる科学的なサイン
持続的な心理的ストレスや「頑張りすぎ」が、コルチゾールの乱れや慢性炎症を引き起こし、免疫システムを攪乱(かくらん)するメカニズムについて解説しました。しかし、こうした体内の変化は、具体的にどのような症状として私たちの日常に現れるのでしょうか。
なんとなく調子が悪い、思考がクリアにならない、あるいは特定の時期に決まって不調になる。これらを気のせいや体質として片付けてしまいがちですが、その多くは身体から送られてくる科学的なサインです。
ここでは、一見すると原因不明に思える日常的な不調の正体について、その背景にある生理学的な関連性を解き明かしていきます。
あの日の思考停止は腸の悲鳴?
重要な会議中や、集中力が必要な作業をしている最中に、突然思考が停止したかのような「ブレインフォグ(脳の霧)」を経験したことはないでしょうか。あるいは、理由のない不安感や気分の落ち込みが続くこともあるかもしれません。これらの脳の症状は、実は腸の状態と密接に関連している可能性があります。
これが、近年非常に注目されている「腸脳相関」と呼ばれる、腸と脳が双方向に情報をやり取りするシステムです。第1章で触れた「最大の免疫器官」である腸は、神経系やホルモン、免疫系を介して、脳の機能や情動に直接的な影響を与えています。
特に重要なのが、第2章で触れた「ストレス」と第1章の「腸管バリア機能」の関係です。強いストレスは、自律神経やホルモンを介して腸の血流を低下させ、腸管バリア(タイトジャンクション)を緩めてしまうことが分かっています。
バリアが破綻(リーキーガット)すると、腸内の未消化物や細菌の断片(LPSなど)が血中に漏れ出し、全身性の慢性炎症を引き起こします。この炎症性物質が脳にまで到達し、脳の神経細胞にダメージを与えたり、神経伝達物質のバランスを崩したりすることで、ブレインフォグや気分の落ち込みといった症状を引き起こすと考えられています。
つまり、あの日の思考停止は、単なる疲れではなく、ストレスによって引き起こされた「腸の悲鳴」が、腸脳相関のルートを通って脳に伝達された結果かもしれないのです。
周期的な不調の正体
特に女性において、月経周期やライフステージの変化(出産後、更年期など)に伴って、体調や気分が大きく変動することは広く知られています。月経前に決まって肌荒れが起きる、風邪をひきやすくなる、あるいは気分が落ち込むといった周期的な不調も、決して「気のせい」ではありません。
これには、エストロゲン(卵胞ホルモン)やプロゲステロン(黄体ホルモン)といった女性ホルモンのダイナミックな変動が、免疫システムに直接作用していることが関与しています。
例えば、エストロゲンは一般的に免疫応答を(適切に)促進する方向に働き、プロゲステロンはむしろ免疫を抑制する方向に働く傾向があります。月経前は、これら両方のホルモンが急激に低下する時期であり、ホルモンによる免疫の調整が不安定になりがちです。
また、免疫細胞自身にも女性ホルモンを受け取る受容体が存在しており、ホルモンバランスの変化が免疫細胞の活動性や、炎症性サイトカインの産生バランスを直接変化させることがわかっています。
さらに、第2章で述べたストレスホルモン「コルチゾール」も、女性ホルモンも、その原材料は同じ「コレステロール」です。慢性的なストレス状態が続き、コルチゾールの産生が優先されると、女性ホルモンの産生が後回しにされてしまうステロイド・スティールと呼ばれる現象が起こる可能性も指摘されています。これがホルモンバランスの乱れを助長し、周期的な不調をさらに悪化させる一因にもなり得ます。
努力を無にする見えない敵
食事に気を使い、良質なサプリメントを摂取し、運動も心がけている。健康のために多くの努力をしているにもかかわらず、一向に不調が改善しない場合があります。その背景には、自分自身の努力だけではコントロールが難しい見えない敵の存在、すなわち環境化学物質の影響が隠れているかもしれません。
私たちは日常生活の中で、知らず知らずのうちに様々な化学物質に曝露されています。例えば、食品添加物、残留農薬、プラスチック製品に含まれる内分泌攪乱物質(いわゆる環境ホルモン)、あるいは大気汚染物質や、マグロなどの大型魚に含まれる水銀といった有害金属などです。
これらの物質の一部は、体内に蓄積すると免疫システムを攪乱したり、神経系に毒性を示したり、あるいはホルモンの働きを妨害したりすることが知られています。
私たちの身体には、これらの有害物質を無毒化し、体外へ排出するための精巧な解毒(デトックス)システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが肝臓です。しかし、この肝臓の解毒機能には個人差がある上、処理能力には限界があります。
有害物質の曝露量が解毒能力を上回ってしまったり、あるいは解毒プロセスに必要な栄養素(タンパク質、ビタミンB群、亜鉛など)が不足していたりすると、有害物質が体内に蓄積し、免疫や代謝の正常な働きを妨害し続けます。
この状態では、いくら良質な栄養素という「アクセル」を踏んでも、有害物質という「ブレーキ」がかかったままでは、身体は思うように機能してくれません。この見えない敵の存在と、自身の「解毒機能」の状態を把握することは、努力を結果につなげるために不可欠な視点です。
まとめ
ここでは、免疫が強い人を支える5つの生理学的原則から、努力が報われない頑張りすぎのパラドックス、そして日常に隠された不調の科学的なサインまでを解説してきました。今、あなたが感じている不調は気のせいや体質ではなく、必ず身体のどこかに原因がある、科学的に説明可能なサインなのです。
そして、ここで触れたように、私たちの免疫システムには遺伝的な個人差があります。つまり、健康への道筋に万人が当てはまる単一の正解は存在しません。
まずはご自身の身体が今、どのような状態にあるのかを客観的なデータで知ることから始めるべきかもしれません。不調の根本原因を可視化する専門的な検査を一度は受けてみてはいかがでしょうか。
アラジン美容クリニック福岡院では、「ウソのない美容医療の実現」をモットーに、患者様お一人ひとりの美のお悩みに真摯に向き合い、最適な治療をご提案しております。無駄な施術を勧めることなく、症状の根本的な原因にアプローチし、患者様の理想を実現するお手伝いをいたします。
また、福岡院限定で提供している特別な施術コース「クマフル」は、目元のクマ治療に特化した定額プランをご用意しております。ハムラ法、脂肪注入、目の下の脂肪取りなど、複数の治療法を組み合わせ、患者様お一人ひとりに最適な治療を提供いたします。目元のクマにお悩みの方は、ぜひこの機会にご利用ください。
LINE公式アカウントにて、カウンセリングや予約を受付しております。どなたでもお使いになられるクーポンもご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。